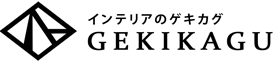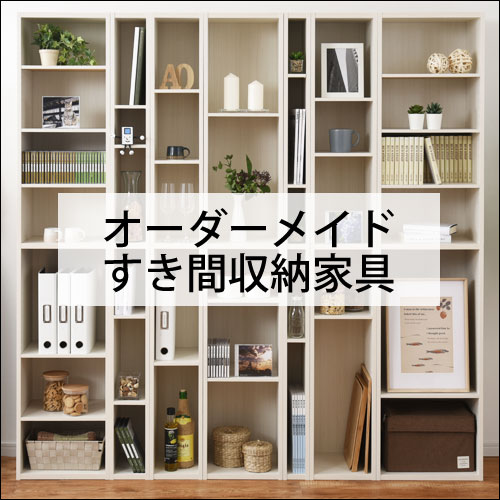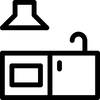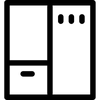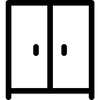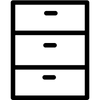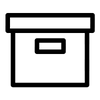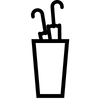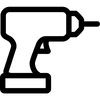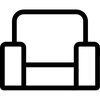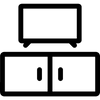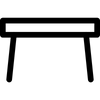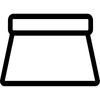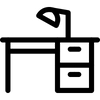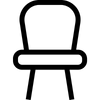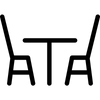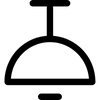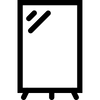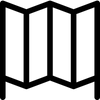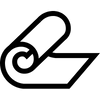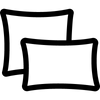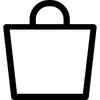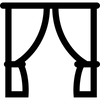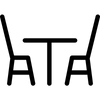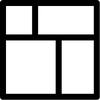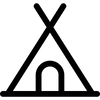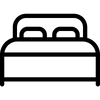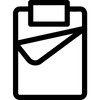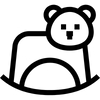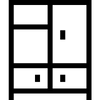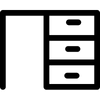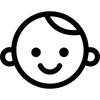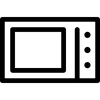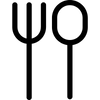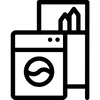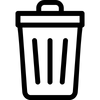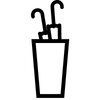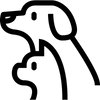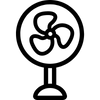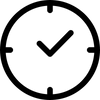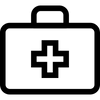チェストとは、衣類収納などに使われる引き出し式の収納家具(整理タンス)のことです。本記事ではチェストの定義や種類(ハイチェスト・ローチェスト・ワイドチェストなど)、用途や素材に応じた選び方、タンスとの違い、さらに収納効率を高めるコツまで、専門家の情報を基にわかりやすく解説します。
チェストとは何か?家具「チェスト」の定義と概要
チェストとは、引き出しのみで構成された収納家具のことです。衣類や小物を分類してしまえることから、日本語では衣類などを整理するための「整理タンス」に相当します。形状は四角い箱状で、前面または上面に複数の引き出しが付いており、衣類や日用品をほこりから守りつつ収納できるのが特徴です。
もともとチェストという言葉は、中世ヨーロッパにおいて蓋付きの長方形の木箱(大きな箱型の収納)を指していました。海賊映画に登場する宝箱のような大型の箱をイメージすると分かりやすいでしょう。その後、17世紀頃になると蓋を上から開ける形式から、前面に引き出しを備えた形式へと進化し、衣類や貴重品を取り出しやすく改良されました。こうして引き出し式収納家具が誕生し、「チェスト・オブ・ドロワーズ(chest of drawers)」と呼ばれるようになります。現在ではこの言葉が省略され、日本語では単に「チェスト」といえば引き出し式の収納家具全般を指すようになっています。
日本で昔から使われてきた「箪笥(たんす)」も、引き出し収納家具である点でチェストとほぼ同義です。ただし箪笥という言葉は和家具(和箪笥)や婚礼家具など伝統的な衣装収納にも使われ、チェストという言葉は洋風デザインの整理タンスや現代的な収納家具に使われる傾向があります。いずれにせよ、チェストもタンスも基本的には衣類や生活用品を収納するための引き出し付き家具であり、現代の住まいには欠かせない存在と言えるでしょう。
チェストの種類
チェストには形状やサイズによってさまざまな種類があり、それぞれ高さや用途が異なります。代表的な分類としては、高さによる違いや横幅(収容力)の違いが挙げられます。ここでは主要なチェストの種類について解説します。
ローチェスト(低いチェスト)
ローチェストは腰の高さ程度までの低めのチェストを指します。もともとは膝くらいの高さで玄関の腰掛けにもなるような箱を指していましたが、現在では一般に腰高(約90cm前後)までの引き出し収納をローチェストと呼びます。横幅は約50~160cmとバリエーションが豊富で、高さを抑えているため圧迫感が少なく、部屋に置いても圧迫感を与えにくいのが利点です。場所を選ばず使いやすいので、リビングや寝室、玄関などどんな部屋にも設置しやすい万能型チェストと言えます。天板(上部)が広いタイプであれば上に飾り物やテレビを置くこともでき、インテリアに調和させやすいでしょう。例えば、背の低いローチェストは上に鏡を置いてドレッサー代わりに使うこともできます。低めのチェストは衣類だけでなく小物類の収納にも適しており、子供でも上段に手が届きやすいため子供部屋用にも人気があります。
ハイチェスト(高いチェスト)
ハイチェストは人の肩ほどの高さがある縦長のチェストです。高さ約100~130cm程度のものが多く、ローチェストに比べて横幅が狭め(一般に40~120cm程度)でスリムな設計になっています。床面積をあまり取らずに引き出しの段数を増やせるため、省スペースで収納量を確保したい場合に適したタイプです。特に収納力が求められる寝室やクローゼット内で重宝します。ただし、高さがあるぶん最上段の引き出しが目線より高くなりがちで、中身を確認しづらいという面もあります。そのため、配置場所によっては圧迫感を与えないか、引き出しの出し入れがしにくくないかを考慮する必要があります。ハイチェストを選ぶ際は、部屋の天井高さとのバランスや、安全のため壁固定具の有無も確認すると安心です。
タワーチェスト(大型チェスト)
タワーチェストは高さが2mを超えるような非常に背の高いチェストです。まさに「タワー」の名が示す通り人の身長以上の高さがあり、引き出しの段数も多く収納力は抜群です。しかし、あまりに高い収納は日常的な使用には向かず、上部の引き出しは手が届きにくくなります。そのため、タワーチェストは主にオフシーズンの衣類や思い出の品など、普段は使わない物の収納に適した家具です。ウォークインクローゼットの中や納戸など、特定の収納空間に設置して季節用品をしまうケースが多く、設置場所や収納物を限定して使われます。天井近くまで収納スペースを確保できる一方、圧迫感も非常に強いため、一般的な居室に置く場合は圧迫感軽減の工夫(壁面と同系色のカラーを選ぶ等)が必要です。
ワイドチェスト(横広のチェスト)
ワイドチェストは横幅が広く取られたタイプのチェストです。明確な定義があるわけではありませんが、一般に横に引き出しが二列以上並んだような幅広のデザインで、高さは抑えめになっているものを指すことが多いです。ローチェストの一種とも言え、幅120~150cm前後など大型で引き出し容量が大きいのが特徴です。幅広のため天板スペースを有効活用でき、置時計や花瓶、写真立てなどを飾ったり、小物を一時的に置いたりしやすいメリットがあります。一方で横に大きい分、設置場所にそれなりの壁面スペースが必要になります。部屋のレイアウト上、ベッドやソファの横手など横長の空きスペースがある場合にワイドチェストを置くと収まりが良いでしょう。ローチェスト同様、圧迫感が少なくインテリアに取り入れやすいので、収納力とデザイン性を両立したい方に人気のタイプです。
その他のチェストの種類
上記以外にも、用途に特化したチェストが存在します。例えばランドリーチェストは洗面所や脱衣所で使うことを想定したチェストで、通気性の良い籐(ラタン)など水に強い素材でできており、タオル類や衣類の一時収納に適しています。またサイドチェストと呼ばれる小型のチェストもあり、横幅が50cm以下程度のコンパクトサイズで、ソファやベッドの脇に置いてサイドテーブル代わりに使ったり、小物整理に活用したりできます。引き出しが小ぶりで細かく分かれているため、文房具やアクセサリーなどの整理にも便利です。さらに、チェストの中には上部に鏡を付けてドレッサー(鏡台)を兼ねたものや、下部にキャスター(車輪)が付いて移動しやすいタイプもあります。このようにチェストにはサイズ・形状ともにさまざまなバリエーションがあり、設置場所や収納物に合わせて適切な種類を選ぶことが重要です。
チェストの選び方:用途・素材・デザイン別のポイント
チェストを選ぶ際には、何を収納するのか(用途)、どんな素材・構造か、そしてデザインや機能性の観点から検討することが大切です。ここではそれぞれの観点で失敗しないチェスト選びのポイントを解説します。
用途別に見るチェスト選びのポイント
チェストに収納したい物や使い方によって、適したチェストのタイプや注目すべき点が変わります。購入前に「何をどこにしまいたいのか」を明確にしておくことで、選ぶべきチェストのイメージが掴みやすくなります。主な用途別にポイントをまとめます。
● 衣類を収納する場合: 毎日着る洋服からシーズンオフの衣類まで、衣類収納が目的なら引き出しの深さに注目しましょう。厚手のセーターやコートなどは畳むと高さが出るため深めの引き出しが必要ですが、薄手のシャツ類ばかりの場合は深すぎる引き出しだと下の服が取り出しにくくなります。洋服の種類に合わせて適切な引き出しの深さ・段数のチェストを選ぶことが大切です。一般的には、高さ控えめで横長のチェスト(ローチェスト)や、引き出しが多段のハイチェストが衣類収納に向いています。また、防虫や防湿のために桐材を用いたチェストを選ぶのも衣類収納では効果的です(これについては後述の素材の項で詳説します)。
● 日用品・小物類を収納する場合: 細々とした生活雑貨や文具、おもちゃなどを収納したいなら、引き出しの数や仕切りに注目します。引き出しが小分けになっているチェストやサイドチェストなら、種類ごとに整理整頓しやすく便利です。印鑑や通帳など貴重品をしまう予定があるなら、鍵付きの引き出しがあるチェストを選ぶと安心です。小物類はつい散らかりやすいですが、チェストに収めてしまえば急な来客時にもサッと隠せて部屋をすっきり見せられます。奥行きの浅いチェストや透明なプラスチックチェストだと中身が一目で分かるので、小物収納にはそうした点も考慮するとよいでしょう。
● テレビ台として使う場合: チェストの中にはリビングでテレビボード代わりに使えるデザインのものもあります。この場合はチェストの高さが重要です。テレビ画面が視聴時の目線と同じかやや下になる高さが理想とされており、床に座る生活なら高さ40cm以下、ソファに座るなら40~60cm程度が目安です。チェストをテレビ台に転用するなら、ローチェストやワイドチェストの中から高さが適切なものを選びましょう。また、引き出し内にリモコンやゲーム機、DVDなどを収納できるとリビングが生活感なくすっきりします。耐荷重も確認して、テレビの重さに十分耐えられる頑丈なチェストを選ぶことも忘れないようにしましょう。
素材別に見るチェスト選びのポイント
チェストに使われている素材や構造も、使い勝手や収納する物への影響を与えます。特に衣類を収納する場合、素材選びは非常に重要なポイントです。伝統的に日本の箪笥では桐材が好まれてきましたが、その理由は桐が衣類収納に適した特性を持つためです。桐(キリ)材は調湿作用があり湿度を一定に保つため防湿効果が高く、さらに虫が嫌う成分タンニンを多く含むことから防虫効果も期待できます。加えて桐は軽量で狂い(変形)が少なく、燃えにくいという利点もあり、日本では古くから衣装箪笥の素材として重宝されてきました。大切な和服や絹製品を収納するなら、桐材で作られたチェストが最適とされるのはこのためです。
一方、洋服ダンスや現代的なチェストにはナラ材やオーク材、ウォールナット材などの広葉樹を使ったものや、パーチクルボードにプリント紙を貼った手頃な製品、樹脂(プラスチック)製のチェストまで素材はさまざまです。無垢材(天然木)を使用したチェストは高級感と耐久性がありますが重量もあります。プリント紙仕上げのチェストは安価で軽く、色柄のバリエーションも豊富ですが、耐久性では無垢材に劣る場合があります。プラスチック製チェスト(衣装ケースタイプ)は軽量で移動が容易なうえ、湿気にも強いのでクローゼット内や子供部屋でよく使われます。ただし耐荷重は木製に比べ低めなので、収納量が多い場合や長く使いたい場合は木製フレームのチェストの方が安心です。
素材選びでは見た目の好みはもちろん、収納物との相性を考えることが大切です。例えば衣類収納なら前述の桐材が最適ですが、リビングで雑貨をしまう程度であればデザイン優先で選んでも問題ありません。化学物質に敏感な方は、接着剤や塗装が少ない無垢材・無着色のチェストを選ぶと安心です。小さなお子様用なら角が丸いデザインや安全な素材かも確認すると良いでしょう。それぞれの素材の長所短所を踏まえ、収納物を守れるチェストを選ぶようにしましょう。
デザイン・機能別に見るチェスト選びのポイント
最後に、チェストのデザインや機能面でチェックしておきたいポイントを紹介します。チェストは部屋のインテリアの一部となる家具ですので、サイズだけでなくデザインや色合いもお部屋に合うか考慮しましょう。シンプルな木目調のチェストは和洋どちらの空間にも合わせやすく、北欧風やヴィンテージ風など部屋のテーマに合わせて材質・色を選ぶと統一感が出ます。また、ローチェストを選べば上に飾り棚的な空間ができますし、ハイチェストを選べば家具の存在感が増します。それぞれの高さによるインテリアへの影響も考慮して選ぶと良いでしょう。足つきのチェストは床が見えて圧迫感が減るうえ掃除がしやすく、逆に直置きタイプは安定感があります。このようなデザイン上の特徴も使い勝手と見た目の両面から検討しましょう。
機能面では、引き出しの構造や開閉のしやすさが特に重要です。毎日使う家具だからこそ、引き出しがスムーズに開閉できることは第一条件と言えます。購入時には実際に引き出しを出し入れしてみて、重すぎないか、引っかかりはないかを確認しましょう。最近では引き出し側面にスライドレールが付いたタイプも多く、重い引き出しでも軽い力で滑らかに開閉できるのでおすすめです。耐久性という点では、引き出し底板に厚みがあるものや、枠組みがしっかりした作り(職人の手によるほぞ組みや箱組構造など)になっているチェストは長持ちします。長期間たくさん物を収納すると底板が抜けることもあるため、「底抜けしない頑丈な構造か」という視点もプロはチェックしています。商品説明に記載があれば参考にすると良いでしょう。
さらに、チェストによって備わる付加機能も選択のポイントです。例えば引き出しにソフトクローズ機能(勢いよく閉めても衝撃を和らげ静かに閉まる機構)が付いたものや、耐震ラッチ(地震時に引き出しが飛び出さない機構)付きのものもあります。子どもが使うなら取っ手の形状や高さも考慮しましょう。引き出しに手を挟まない構造か、小さな力でも開けられるかといった点です。また、チェスト自体の重量が重い場合は設置後の移動が難しいため最初の配置計画をしっかり立てる、一方軽量な組立式チェストの場合は強度を確認するといった配慮も必要です。最後に、見た目については部屋の雰囲気になじむかどうかだけでなく、毎日目にして愛着が持てるデザインかという点も大切です。機能とデザインのバランスを考え、自分のライフスタイルにフィットするチェストを選びましょう。
チェストとタンス(箪笥)の違い
チェストとタンスという言葉は、しばしば同じ意味で使われますが、その背景には洋家具と和家具の違いがあります。チェストは上述のように西洋発祥の引き出し家具ですが、タンス(箪笥)は日本で発達した収納家具です。もっとも、現代ではチェスト=タンスと考えて差し支えないほど機能的な違いはありません。ここでは歴史的・文化的な違いに着目して両者を見てみましょう。
語源と歴史の違い
「チェスト(Chest)」は英語で「箱」「胸部」などを意味しますが、家具としては前述の通り蓋付きの箱型収納をルーツに持ち、後に「チェスト・オブ・ドロワーズ(chest of drawers)」=引き出し付きの箱家具を指すようになりました。一方「箪笥(たんす)」は中国から伝来したとされる言葉で、日本で独自の発展を遂げました。日本初の箪笥は江戸時代前期の寛文年間(1660年代)に大阪で作られ始めたと言われており、当初は豪商の帳簿入れや薬種商の薬入れなど、小さな引き出しが多数ついた和家具として利用されていました。例えば江戸時代の薬箪笥(くすりダンス)では、引き出し一つ一つに薬種名を書いて整理できるようになっていました。下の写真は引き出しが多数並んだ古い和箪笥の例です。このように、西洋では蓋付きの大箱から発展し東洋では細かな引き出しから発展したという起源の違いがあるのです。
呼び方・デザインの違い
現代の日本では、チェストもタンスも共に引き出し収納家具を指すことが多いですが、強いて区別するとすれば使う場面やデザインによる呼び分けがあります。例えば、「和箪笥」という場合は和室に合う伝統的デザインの箪笥を指し、桐箪笥や婚礼家具など重厚な造りのものが多いです。一方「チェスト」は洋室や現代的インテリアに置くカラフル・シンプルな整理ダンスを指すことが多くなっています。また、「脚の有無で呼び分ける」という意見もあり、脚付きで床から浮いたデザインのものをチェスト、床にベタ置きのものをタンスと呼ぶ人もいるようです。しかしこの区別は明確な基準ではなく、人やメーカーによって異なります。
機能上の違い
チェストとタンスには基本的に大きな機能差はありませんが、箪笥という言葉には引き出し以外の構造も含む広い意味合いがある点に注意しましょう。箪笥には整理箪笥(チェスト)以外に、着物を平たく収納するための衣装箪笥(桐箪笥)、洋服をハンガーに掛けて収納する洋服箪笥(ワードローブ)、食器を収納する水屋箪笥、茶道具を飾る茶箪笥など様々な種類があります。これらは引き出しだけでなく扉や棚板を備えたものも多く、収納対象に特化した構造になっています。対して「チェスト」という場合は基本的に引き出し構造の収納を指します。つまり、洋服タンスのような扉付きの大型家具はチェストとは呼ばれない傾向があります(英語ではワードローブと呼ぶ)。このような点を踏まえると、チェストとタンスの違いは文化的な呼称の違いであり、狭義には「チェスト=引き出しだけの収納」「タンス=引き出し含む様々な衣類収納家具」と区別できる程度と言えるでしょう。実際の家具選びにおいては、呼び名の違いよりもデザイン・サイズ・機能をよく確認することの方がずっと重要です。
チェスト収納のコツと設置場所のポイント
最後に、手に入れたチェストを最大限活用するための収納テクニックと、チェストを置く上で知っておきたい設置場所のポイントを紹介します。
チェストの収納効率を高めるコツ
チェストは引き出しの中に物をしまって扉を閉めてしまうため、油断すると中が乱雑になりがちです。しかし一工夫することで驚くほど収納効率がアップし、使いやすくなります。ポイントは「上から見渡せる収納」にすることです。具体的には、以下のコツが有効です。
● 引き出し内を仕切る: 大きな引き出しの中身がごちゃ混ぜにならないよう、用途に応じて仕切りを使いましょう。100均の仕切りケースや空き箱、専用の整理ボックス(例:「せいとんボックス」など)を活用すると、引き出し内が区画化され物が探しやすくなります。靴下や下着など細かい物は小分けに、衣類も種類別・用途別にエリアを決めて入れると見た目にもスッキリします。
● 洋服は立てて収納する: 衣類を引き出しに入れる際は、畳んだ服を垂直に立てて並べるように収納するのがおすすめです。平積みにすると上から見て一番上の服しか見えませんが、丸めたり畳んだ服を立てて収納すれば引き出しを開けたときに全ての衣類が一目で見渡せるようになります。取り出しも簡単になり、持っている服の把握がしやすくなるため、重複買いや着忘れの防止にもつながります。畳んだ衣類は折り目が上になるように立てると自立しやすく、取り出しても崩れにくいです。幅広の引き出しなら前述の仕切りを入れて区分けすると、さらに整然と収納できます。
● しまう場所を決める: チェストやタンスの中で「どこに何を入れるか」をあらかじめ決めておくと、出し入れがスムーズで散らかりにくくなります。一つの引き出しには一種類の物(または一カテゴリの服)だけを入れるようにし、ラベルを貼っておくのも良い方法です。使用頻度に応じて収納場所の高さを変えることも大事です。例えば毎日着る洋服や下着類は立ったままでも手に取りやすい上段に、逆にシーズンオフの衣類や思い出の品は下段に入れるなど、使う頻度に合わせて収納場所を決めると使い勝手が向上します。定期的に中身を見直して不要な物を処分すれば、新たな収納スペースも生まれて一石二鳥です。
チェストを設置する場所と配置のポイント
チェストは比較的自由に置ける家具ですが、置く場所によって使い勝手が変わります。まず、チェストを置く部屋は収納する物に合わせて選ぶのが基本です。例えば衣類用のチェストなら寝室やクローゼットの中、日用品を入れるならリビング、子供のおもちゃや洋服なら子供部屋、といった具合です。あらかじめ収納目的を決め、その物を使う場所の近くに置くことで、家事動線がスムーズになります。
設置時にはスペースの採寸も忘れずに行いましょう。チェスト本体の幅・奥行き・高さが収まるかだけでなく、引き出しをいっぱいに引いたとき人が通れる余裕があるか、上部に扉棚がある場合干渉しないかなどを確認します。特に寝室や廊下など狭い場所では、引き出しを引くための前方スペースが確保できるか要チェックです。可能であれば設置場所の壁の下地(柱の位置)を調べ、必要に応じて家具転倒防止金具でチェストを壁に固定すると安全面でも安心です。高さのあるチェストは地震の際に倒れるリスクがあるため、L字金具などで固定できるとベターです。
また、チェストは日当たりや湿度にも気を配りたい家具です。直射日光が長時間当たる場所に木製チェストを置くと、日焼けや反りの原因になることがあります。カーテン越しの柔らかな日差しが当たる程度なら問題ありませんが、必要に応じてカバーや布を掛けると良いでしょう。湿気がこもりがちな洗面所や玄関に置く場合は、防カビ剤や除湿剤を引き出しの隅に入れておくとカビ対策になります。逆に暖房の風が直接当たる場所では乾燥しすぎて木材が割れることもあるため注意しましょう。
配置の工夫として、ローチェストであれば窓下の空いたスペースに収める、ハイチェストであれば壁の一角にまとめて配置して視界を遮らないようにする、といった方法があります。複数のチェストを並べる場合は高さやデザインを揃えると圧迫感が軽減され、見た目も整います。部屋の導線を妨げない位置に置き、必要な場所に必要な物がしまってある状態を作ることが、チェストを有効活用するコツです。
まとめ
チェストについてその定義から種類、選び方、タンスとの違い、収納術まで幅広く解説しました。チェストは収納力とインテリア性を兼ね備えた心強い家具です。本記事の内容を参考に、自宅にぴったりのチェストを選んで快適で美しい暮らしを実現してください。各種メーカーや専門店の情報も活用しながら、ぜひ納得のいく一台を見つけましょう。