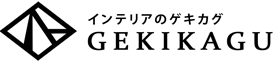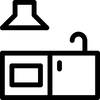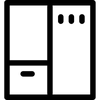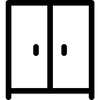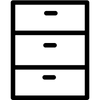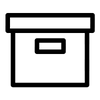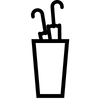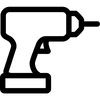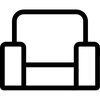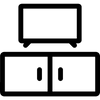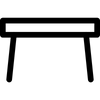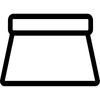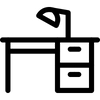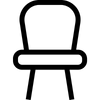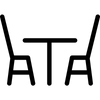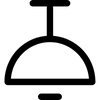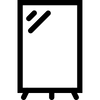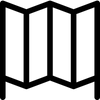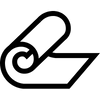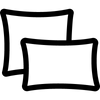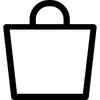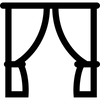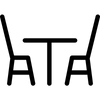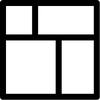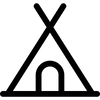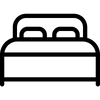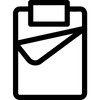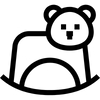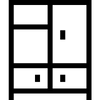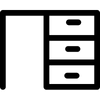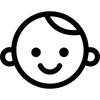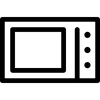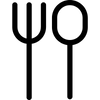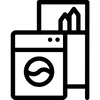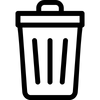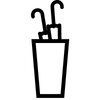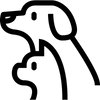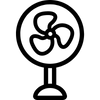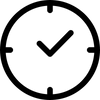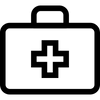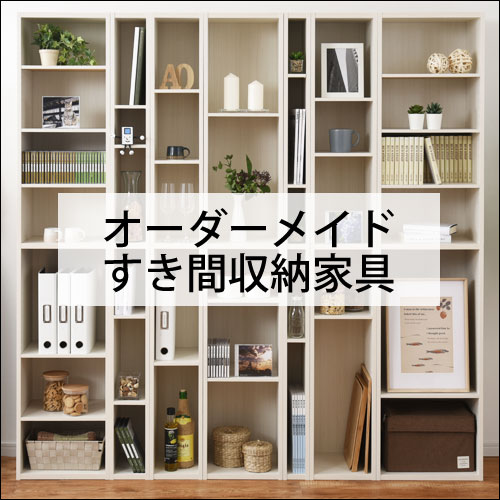カラーボックス×インナーボックス活用術|おしゃれ収納を叶える選び方
カラーボックスとインナーボックスで収納が変わる!基本知識から選び方、おしゃれな整理術までプロが解説。リビングや子供部屋、クローゼットで役立つ実践アイデア満載。

万能収納の定番!カラーボックスの特徴とは?
手軽さとアレンジの自由度から、収納家具の定番として長年愛され続けているカラーボックス。一人暮らしのスタートからファミリー層まで、あらゆるライフステージで活躍するアイテムです。まずは、その基本的な特徴と魅力、そして可能性について深く掘り下げてみましょう。
カラーボックスが愛される理由
カラーボックスがこれほどまでに普及し、多くの人に支持されるのには明確な理由があります。
- 手頃な価格: なんといっても最大の魅力はそのコストパフォーマンスの高さ。気軽に購入し、数を増やしたり、買い替えたりしやすいのが特徴です。
- シンプルな構造: 基本的には棚板と側板で構成されるシンプルな作りで、組み立ても比較的簡単です。DIY初心者でも扱いやすい点が魅力です。
- 汎用性の高さ: リビング、寝室、子供部屋、書斎、クローゼット、キッチン周りなど、家中のあらゆる場所で活躍します。縦置き・横置きどちらでも使えるタイプも多く、設置場所を選びません。
- 入手しやすさ: 家具店だけでなく、ホームセンターやオンラインストアなど、様々な場所で手軽に購入できます。
基本的な構造とサイズ感
カラーボックスの多くは、規格化されたサイズで作られています。一般的にはA4ファイルが縦に収まる程度の奥行きと棚の高さを持つ3段タイプが主流ですが、2段、4段、5段といったバリエーションも豊富です。この「規格化されている」という点が、後述するインナーボックスとの組み合わせにおいて非常に重要なポイントとなります。オープンラック構造が基本で、背面が開いているタイプ、背板が付いているタイプがあります。
メリットとデメリット
万能に見えるカラーボックスにも、メリットとデメリットがあります。
● メリット:
○ 価格が安く、導入しやすい。
○ サイズや色のバリエーションが豊富。
○ 軽量で移動や配置換えが比較的容易。
○ インナーボックスやDIYでカスタマイズしやすい。
● デメリット:
○ 素材によっては安価に見えやすい場合がある。
○ オープン棚のため、中身が見えて雑多な印象になりやすい。
○ 耐荷重に限りがあり、重いものを載せすぎると棚板がたわむことがある。
○ 湿気に弱い素材のものもある。
これらのデメリット、特に「中身が見えて雑多な印象になりやすい」点を解決してくれるのが、インナーボックスの存在なのです。
種類とバリエーション
基本的な直方体のオープンラック以外にも、カラーボックスには様々な種類があります。
● 段数の違い: 2段、3段、4段、5段など。
● 扉付きタイプ: 中身を完全に隠せる扉付きのカラーボックス。
● コーナータイプ: 部屋の角を有効活用できるL字型のタイプ。
● スリムタイプ: 狭いスペースにも置きやすい奥行きや幅が小さいタイプ。
● キューブタイプ: 正方形に近い形状で、自由に積み重ねたり組み合わせたりできるタイプ。
カラーボックスを格上げ!インナーボックスの特徴
カラーボックスの使い勝手と見た目を劇的に向上させるアイテム、それが「インナーボックス」です。ここでは、インナーボックスが持つ役割、素材や形状の種類、そして導入するメリットについて解説します。
インナーボックスとは?その役割と魅力
インナーボックスとは、その名の通り、カラーボックスの棚(スペース)にぴったり収まるように設計された収納ボックスのことです。主な役割と魅力は以下の通りです。
- 整理整頓: 細かいものをカテゴリー別に分け、ボックスごとに出し入れできるようにすることで、棚の中が整理されます。
- 目隠し効果: ごちゃごちゃしがちな中身を隠し、生活感を抑えてすっきりとした見た目を実現します。
- 空間の演出: 素材や色を工夫することで、カラーボックス自体の印象を変え、インテリアの一部として空間をおしゃれに演出します。
- ホコリ除け: ボックスに入れることで、中の物がホコリをかぶるのを防ぎます。
素材による違いと選び方
インナーボックスは様々な素材で作られており、それぞれ特徴が異なります。用途や置く場所、目指すインテリアのテイストに合わせて選びましょう。
● 布製(不織布、ポリエステル、綿、麻など):
○ メリット: 軽量で扱いやすく、折りたためるタイプが多い。色柄が豊富。ナチュラルで柔らかい印象を与える。
○ デメリット: 型崩れしやすい場合がある。汚れが染み込みやすい。湿気に弱い。
○ 選び方: 子供のおもちゃや衣類、タオルなど、軽いものの収納に。リビングや寝室など、優しい雰囲気にしたい場所に。芯材が入っているか確認すると型崩れしにくい。
● プラスチック製:
○ メリット: 耐久性、耐水性が高い。汚れを拭き取りやすい。スタッキング可能なタイプもある。
○ デメリット: 無機質で冷たい印象になりやすい。静電気でホコリが付きやすい場合がある。
○ 選び方: キッチン周りの食品ストックや洗剤、洗面所のタオルや小物、子供部屋の汚れやすいおもちゃなど、水濡れや汚れが気になる場所に。
● 紙製(硬質パルプ、ダンボールなど):
○ メリット: 軽量で比較的安価。デザイン性が高いものも多い。リサイクル可能。
○ デメリット: 水濡れや湿気に非常に弱い。耐久性は他の素材に劣る。
○ 選び方: 書類や雑誌、文房具など、水濡れの心配が少ない乾いたものの収納に。書斎やリビングなど。
● 天然素材(ラタン、シーグラス、ウォーターヒヤシンス、竹など):
○ メリット: ナチュラルで温かみのある雰囲気。通気性が良い。インテリア性が高い。
○ デメリット: 価格が高め。ささくれなどで引っかかることがある。ホコリが溜まりやすい場合がある。
○ 選び方: リビングや寝室で、見せる収納として。衣類やブランケットなど、通気性を保ちたいものの収納に。アジアンテイストや北欧ナチュラルテイストのインテリアに。
形状や機能性のバリエーション
基本的な立方体だけでなく、使い勝手を高める様々な形状や機能を持つインナーボックスがあります。
● サイズ: カラーボックスの棚に合わせたフルサイズ、棚を半分に仕切れるハーフサイズなど。
● 蓋(フタ)付き: ホコリを防いだり、中身を完全に隠したり、スタッキングしやすくしたりするのに便利。
● 取っ手付き: 引き出しのようにスムーズに出し入れが可能。前面だけでなく、両サイドに付いていると持ち運びに便利。
● 仕切り付き: 靴下や下着、アクセサリーなど、細かいものをボックス内でさらに分類するのに役立つ。
● 折りたたみ式: 使わない時にコンパクトに収納できる。
インナーボックス導入のメリット
改めて、インナーボックスを使うことのメリットを整理しましょう。
● 雑多なものを隠せる: カラーボックスのオープン棚のデメリットを解消。
● 分類・整理が容易になる: 「おもちゃ」「文房具」「シーズンオフの衣類」など、ボックスごとに中身を決めることで、誰でも簡単に整理できる。
● インテリア性が向上する: 素材や色を揃えることで、統一感が生まれ、おしゃれな印象に。
● 収納物の保護: ホコリや日焼けから中の物を守る。
カラーボックスとインナーボックスを使った整理収納術
カラーボックスとインナーボックスの特性を理解した上で、具体的な活用シーンと整理収納のアイデアを見ていきましょう。場所や目的に合わせて工夫することで、その可能性は無限に広がります。
リビング:散らかりがちな小物をすっきり隠す
リビングは家族が集まる場所であり、リモコン、充電器、雑誌、読みかけの本、ひざ掛けなど、様々なものが散らかりがちです。
● 定位置管理: アイテムごとにインナーボックスを割り当て、「リモコン・充電器」「読み物」「お菓子」など、定位置を決めます。
● デザイン性の高いボックスを選ぶ: リビングの雰囲気に合わせて、ラタンや布製など、インテリアに馴染む素材や色のボックスを選び、「見せる収納」を意識します。
● 一時置き場として: すぐに片付けられない書類や郵便物などを一時的に入れておく「とりあえずボックス」を作ると、テーブルの上が散らかりません。中身がいっぱいになったら整理するルールを設けましょう。
子供部屋:おもちゃや学用品を楽しく分類
増え続けるおもちゃや学用品の整理は、子供部屋の大きな課題です。
● 子供にも分かりやすく: ボックスの色を変えたり、写真やイラストのラベルを貼ったりして、「ぬいぐるみ」「ブロック」「お絵かき道具」「教科書」など、子供自身がどこに何をしまうか分かるように工夫します。
● ポイポイ収納: 細かく分類しすぎず、大きめのボックスを用意して、ざっくりと投げ込むだけの「ポイポイ収納」を取り入れると、子供も片付けのハードルが下がります。
● 安全性: 子供が使う場合は、軽量で角が丸い布製や、柔らかいプラスチック製のボックスを選ぶと安全です。
クローゼット・押し入れ:衣類や小物を効率的に収納
奥行きがあって使いこなしにくいクローゼットや押し入れも、カラーボックスとインナーボックスで劇的に改善できます。
● カテゴリー別収納: シーズンオフの衣類、バッグ、帽子、マフラー・手袋などのファッション小物、下着・靴下などを、ボックスごとに分類します。
● 縦の空間を活用: カラーボックスを横置きにしてインナーボックスを引き出しのように使ったり、縦置きにして棚ごとにアイテムを分けたりします。
● 中身がわかる工夫: 不透明なボックスには、ラベルを貼ったり、タグを付けたりして、開けなくても中身がわかるようにします。衣替えもボックスごと入れ替えるだけで楽になります。
キッチン・パントリー:食品ストックや雑貨を整理
食品ストック、調味料、お弁当グッズ、掃除用品など、キッチン周りも物が多い場所です。
● 衛生面を考慮: 汚れを拭き取りやすいプラスチック製のボックスが適しています。
● グルーピング: 「レトルト・缶詰」「乾物」「お菓子」「掃除用品」など、関連するものをまとめてボックスに入れると、在庫管理がしやすくなります。
● 取り出しやすさ: 取っ手付きのボックスを選ぶと、棚の奥の物もスムーズに取り出せます。
ワンランク上の見せ方・使い方テクニック
基本的な使い方に加えて、少し工夫するだけで、さらに使いやすくおしゃれに見せることができます。
● オープン棚とのメリハリ: 全ての棚をインナーボックスで埋めるのではなく、お気に入りの雑貨や本を飾る「見せる棚」と、インナーボックスで「隠す棚」を組み合わせると、空間にリズムが生まれます。
● ボックスを引き出し風に: カラーボックスを横置きにして、取っ手付きのインナーボックスを入れると、簡易的な引き出し収納として使えます。
● ラベリングにこだわる: 手書きのラベル、おしゃれなテンプレートを使ったラベル、タグなど、ラベリング自体をデザインの一部として楽しみます。
● 色や素材のコーディネート: 部屋全体のインテリアテーマに合わせて、インナーボックスの色や素材を選び、統一感を出します。複数の色を使う場合も、トーンを合わせるとまとまりやすくなります。
インナーボックス選びで失敗しないための注意点
せっかくインナーボックスを導入しても、「サイズが合わなかった」「すぐに壊れてしまった」となっては残念です。購入前に確認すべきポイントを押さえておきましょう。
サイズ確認は絶対!内寸を測ろう
最も重要なのがサイズ確認です。「カラーボックス用」と書かれていても、メーカーや製品によってカラーボックス自体のサイズ、特に棚の内寸(幅・高さ・奥行き)は微妙に異なります。必ず、お持ちのカラーボックスの棚の内寸をメジャーで正確に測り、それに合ったサイズのインナーボックスを選びましょう。数ミリの違いで入らない、あるいは隙間が空きすぎる、といったことが起こりがちです。
耐荷重と強度を考慮する
何を収納するかによって、ボックスに必要な強度や耐荷重は変わってきます。本や書類、缶詰など重いものを入れる場合は、底板がしっかりしているか、側面が丈夫な素材(硬質パルプや厚手のプラスチックなど)でできているかを確認しましょう。布製でも芯材がしっかり入っているものを選びます。
用途と設置場所に適した素材を選ぶ
前述の通り、素材にはそれぞれ特性があります。湿気の多い洗面所やキッチンには耐水性の高いプラスチック、子供部屋には安全で軽量な布製、書斎には紙製、リビングには見た目重視の天然素材など、用途と設置場所の環境に適した素材を選びましょう。
部屋全体のテイストとの調和
インナーボックスは収納用品であると同時に、インテリアを構成する要素でもあります。部屋の壁紙、床、他の家具との色合いや素材感を考慮し、空間全体として調和のとれたものを選びましょう。アクセントとして敢えて対照的な色を選ぶのもテクニックですが、全体のバランスを見ることが大切です。
まとめ
カラーボックスとインナーボックスは、それぞれ単体でも便利なアイテムですが、組み合わせることでその真価を発揮し、収納の可能性を大きく広げてくれます。「隠す」「分類する」「飾る」を自在にコントロールし、手軽に、そしておしゃれに整理整頓を実現できる最高のコンビネーションと言えるでしょう。
この記事でご紹介した特徴、選び方、活用アイデア、注意点を参考に、ぜひあなたの家でもカラーボックスとインナーボックスを使った快適な収納づくりに挑戦してみてください。きっと、日々の暮らしがよりスムーズで心地よいものになるはずです。