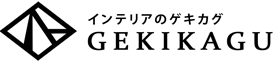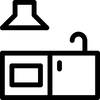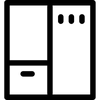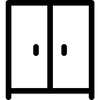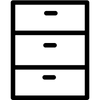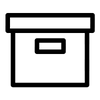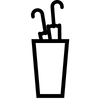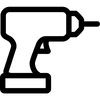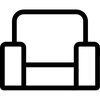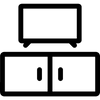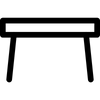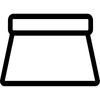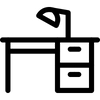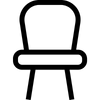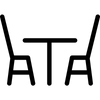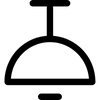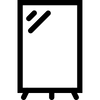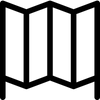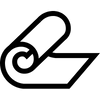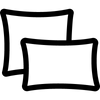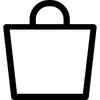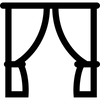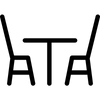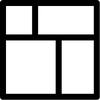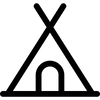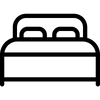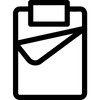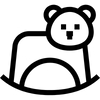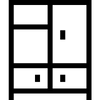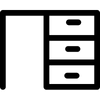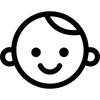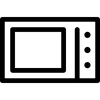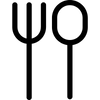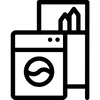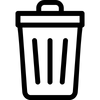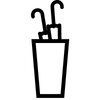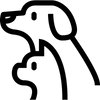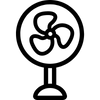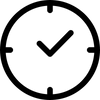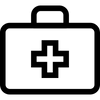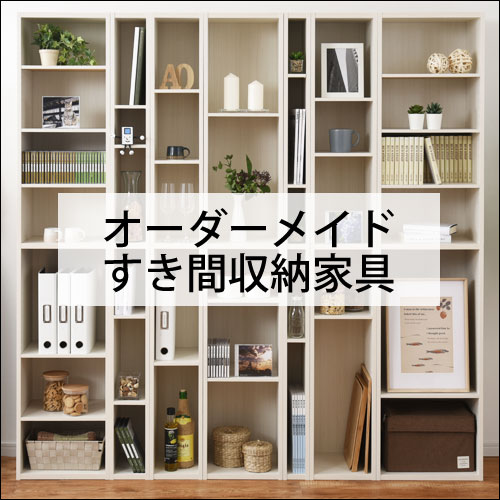食材や日用品のストックに便利なパントリーですが、気づけば奥から古い食品が出てきたり、どこに何があるかわからないカオス状態になったりしがちです。その問題を解決する鍵は「収納ボックス」の賢い活用にあります。この記事では、パントリー収納の基本的な考え方から、なぜ収納ボックスを使うべきなのか、そしてあなたのパントリーに最適な収納ボックスの選び方まで、専門家の視点で徹底解説。美しく機能的なパントリーを実現し、日々の家事をぐっと楽にするためのヒントが満載です。

そもそもパントリーとは?キッチンを支える重要な収納スペース
理想の家づくりで人気が高まっている「パントリー」。まずは、その基本的な役割と種類について理解しておきましょう。
食材や日用品をストックする「食品庫」
パントリーとは、キッチンに隣接または近接して設けられる収納スペースのことで、日本語では「食品庫」と訳されます。常温で保存できる食材、飲料、調味料のストックをはじめ、普段は使わない調理器具や、キッチンペーパー、洗剤といった日用品まで、キッチン周りのあらゆるモノをまとめて収納しておくための空間です。パントリーがあることで、キッチンの作業スペースをすっきりと保ち、買い物に行く頻度を調整できるなど、多くのメリットがあります。
ウォークイン型から壁面型まで多様なスタイル
パントリーにはいくつかのタイプがあります。人が中に入れる小部屋のような「ウォークイン型」や「ウォークスルー型」は、大容量の収納が魅力です。一方で、キッチンの壁の一角や、食器棚の一部を利用した「壁面型(キャビネット型)」は、省スペースで導入しやすいのが特徴です。どのタイプのパントリーであっても、その収納力を最大限に引き出すための基本的な考え方は共通しています。
"ごちゃごちゃ"を防ぐ!美しく機能的なパントリー収納の3つの鉄則
パントリーを単なる物置きにせず、機能的な空間として維持するためには、守るべき3つの鉄則があります。収納ボックスを選ぶ前に、まずはこの基本を押さえましょう。
鉄則1:使用頻度と仲間で分ける「ゾーニング」
まず、パントリー全体をエリア分け(ゾーニング)します。基本は「使用頻度」です。毎日〜週に数回使うモノは、最も取り出しやすい「目線から腰の高さ」のゴールデンゾーンに。月に数回程度のモノは、少し屈むか手を伸ばす場所に。そして、年に数回しか使わないモノや大量のストック品は、一番上か一番下の段に配置します。さらに、「レトルト食品」「缶詰」「粉物」「お菓子」といったように、同じ種類の仲間でグルーピングすることも重要です。
鉄則2:在庫管理を楽にする「ラベリング」
特に中身が見えない収納ボックスを使う場合、どこに何が入っているかわからなくなりがちです。これを防ぐのが「ラベリング」です。ボックスの前面に「パスタ・乾麺」「缶詰」「お菓子」など、中身が一目でわかるラベルを貼りましょう。これにより、物を探す時間が短縮されるだけでなく、家族の誰もが必要な物を見つけられるようになります。在庫の二重買いを防ぐ効果も絶大です。
鉄則3:無理なく続ける「ローリングストック法」
パントリーは、防災備蓄の観点からも非常に重要な役割を果たします。そこでおすすめなのが「ローリングストック法」です。これは、普段から少し多めに食材をストックしておき、賞味期限の古いものから消費し、消費した分だけを買い足していく方法です。これにより、常に一定量の食料を備蓄しつつ、食品ロスを防ぐことができます。収納する際は「手前に古いもの、奥に新しいもの」を置くルールを徹底しましょう。
なぜ必要?パントリーに収納ボックスを導入すべき理由
ゾーニングやラベリングを実践する上で、欠かせないのが「収納ボックス」です。なぜボックスを使うと、パントリー収納は劇的に改善するのでしょうか。
理由1:見た目の統一感で「生活感を隠す」
色や形がバラバラな食品パッケージは、それだけで雑然とした印象を与えます。同じシリーズの収納ボックスにまとめて入れるだけで、見た目が驚くほどすっきりと整い、生活感を上手に隠すことができます。扉のないオープンなパントリーでも、統一感のあるボックスが並んでいるだけで、モデルルームのような美しい空間を演出できます。
理由2:空間を無駄なく使う「スタッキング効果」
同じ種類の収納ボックスを使えば、きれいに積み重ねる(スタッキングする)ことが可能です。これにより、棚の高さ方向の空間を無駄なく活用し、収納力を最大限に引き出すことができます。棚板の間隔が広く、上がデッドスペースになりがちな場合に特に有効な方法です。
理由3:中身を把握しやすくする「グルーピング効果」
「缶詰グループ」「お菓子グループ」といったように、仲間ごとにボックスに入れることで、モノの住所が明確になります。ボックスごと取り出せば、奥にある物も簡単に確認でき、在庫管理が非常に楽になります。「なんとなく」で置いていたモノたちに定位置を与えることで、パントリー全体の把握が容易になるのです。
失敗しない!パントリー用収納ボックスの賢い選び方
では、実際にどのような収納ボックスを選べば良いのでしょうか。失敗しないための4つの選び方のポイントをご紹介します。
ポイント1:棚の奥行きと幅に合わせた「サイズ選び」
最も重要なのがサイズです。まずは、パントリーの棚の「奥行き」と「幅」を正確に採寸しましょう。特に奥行きは重要で、棚板の奥行きにぴったりのボックスを選ぶと、奥に無駄なスペースが生まれず、収納力を最大限に活かせます。幅の違うボックスをパズルのように組み合わせて、棚の横幅にシンデレラフィットさせることを目指しましょう。
ポイント2:収納物で決める「素材選び」(プラスチック、布、ファイルボックス等)
収納する物によって、適した素材は異なります。調味料のボトルなど、液だれの可能性があるものには、汚れても拭きやすいプラスチック製が安心です。お菓子やパンなど、軽く通気性を保ちたいものには、布製や不織布製のソフトボックスが向いています。また、意外な万能選手がファイルボックスです。レトルト食品やラップ類のストックなどを「立てて収納」するのに最適で、すっきり整理できます。
ポイント3:使い勝手を左右する「形状」(取っ手・蓋の有無)
高い場所に置くボックスには、安全に取り出すための「取っ手」が必須です。前面に手や指を掛けられる穴やハンドルが付いているタイプを選びましょう。ホコリが気になるものや、中身を完全に隠したい場合は「蓋つき」が便利ですが、アクションが一つ増えるので、使用頻度の高いものには蓋なしを選ぶなど、バランスを考えることが大切です。
ポイント4:モチベーションを上げる「デザインの統一感」
毎日目にする場所だからこそ、デザインの統一感は整理整頓のモチベーションを維持する上で意外と重要です。白やグレー、半透明などのベーシックな色で揃えると、清潔感のあるすっきりとした印象になります。自分の好きなテイストで揃えることで、パントリーがお気に入りの空間になり、きれいに保とうという意識も高まります。
【タイプ別】おすすめ収納ボックス活用アイデア
最後に、具体的なボックスの種類ごとにおすすめの活用アイデアをご紹介します。
定番の「ファイルボックス」で立てる収納
書類整理の定番であるファイルボックスは、パントリー収納の救世主です。袋入りのレトルト食品や、スパイスの小瓶、ラップやアルミホイルのストックなど、自立しにくいものを「立てて収納」するのに最適。一覧性が高く、さっと取り出せます。
中身が見える「半透明のプラスチックケース」
パスタや乾物、シリアルなど、残量が一目でわかると便利なものの収納には、中身がうっすらと透けて見える半透明のケースがおすすめです。ラベリングをしなくても中身を把握できる手軽さが魅力です。
高い場所でも安心な「取っ手付きソフトボックス」
キッチンペーパーのストックやお菓子類など、軽くてかさばるものは、布製などの軽いソフトボックスに入れるのが最適です。万が一、高い場所から落としてしまっても、被害が少なく安全です。取っ手が付いていれば、出し入れも簡単です。
まとめ
パントリーは、正しい知識で整理すれば、キッチンの使い勝手を劇的に向上させてくれるポテンシャルの高い空間です。その鍵を握るのが、あなたの家のパントリーとライフスタイルに合った「収納ボックス」を選ぶこと。「ゾーニング」「ラベリング」「ローリングストック」という3つの鉄則をベースに、最適なボックスを導入すれば、在庫管理が楽になり、食品ロスが減り、そして何より美しい空間が手に入ります。この記事を参考に、理想のパントリー作りを始めてみませんか。