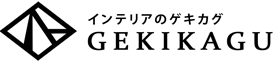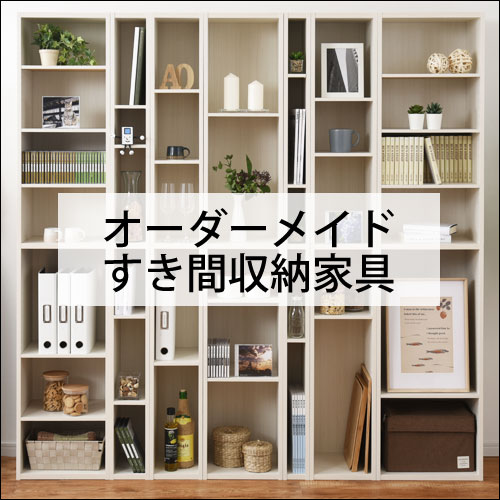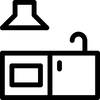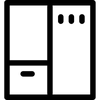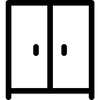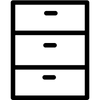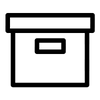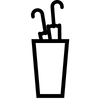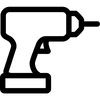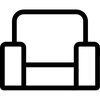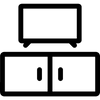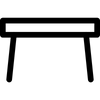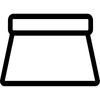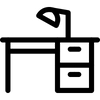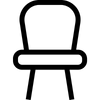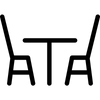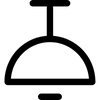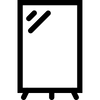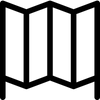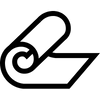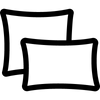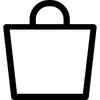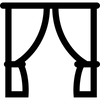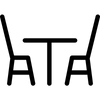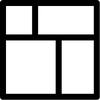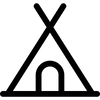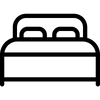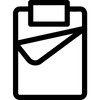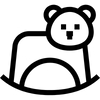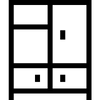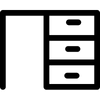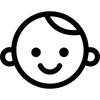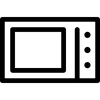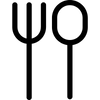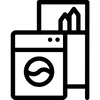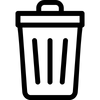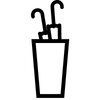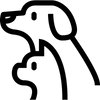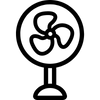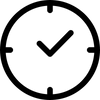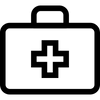ランドセルラックは、子供の片付け習慣を育む上で便利な一方、選び方や使い方を間違えると「使われない家具」になってしまうことがあります。この記事では、ランドセルラック購入で失敗しがちなパターンを具体的に解説し、そこから学ぶ上手な活用方法と、後悔しないための選び方のポイントを専門家の視点で詳しくご紹介します。ラックの必要性を見極めることから、卒業後まで長く使える製品選びまで、この記事を読めば、お子様にとってもご家庭にとっても最適なランドセルラックの答えが見つかります。
ランドセルラックは必要?不要?購入前に考えるべきこと
新入学の準備を進める中で、多くの保護者の方が一度は「ランドセルラックって、本当に必要なのだろうか?」という疑問に直面します。学習机とセットで検討されることも多いこの家具ですが、その必要性はご家庭の環境や教育方針によって大きく異なります。購入してから「なくてもよかったかも…」と後悔しないために、まずは必要派と不要派、両方の意見を知り、我が家にとっての最適解を探ってみましょう。
「必要派」の意見:片付け習慣が身につく環境づくり
ランドセルラックを推奨する最大の理由は、子供の「お片付け習慣」を自然にサポートできる点にあります。子供にとって「ここが自分のランドセルと学用品の置き場所」という明確な定位置があることは、自分で持ち物を管理する意識の第一歩です。散らかりがちな教科書、ノート、プリント類を一か所にまとめることで、紛失を防ぎ、翌日の準備もスムーズに行えるようになります。子供が自分で整理整頓しやすい環境を物理的に整えてあげることは、自立心を育む上で非常に有効なアプローチと言えるでしょう。
「不要派」の意見:他の家具でも代用可能という考え方
一方で、「不要である」という意見にも耳を傾ける価値があります。その主な理由は、他の家具で十分に代用できるという点です。例えば、リビングに設置したカラーボックスや、既存の収納棚の一角をランドセル置き場として活用することも可能です。また、小学校の6年間という限られた期間しか使わない可能性を考えると、専用の家具を増やすことに抵抗を感じるご家庭も少なくありません。「リビング学習が中心だから、ランドセルの置き場所もリビングの棚で十分」という判断も、一つの合理的な選択です。
我が家に必要かを見極める3つのポイント
最終的にランドセルラックが必要かどうかは、ご家庭の状況によります。判断に迷った際は、以下の3つのポイントを検討してみてください。
- 学習場所はどこか?: リビングで学習するのか、子供部屋で学習するのか。学習場所とランドセル置き場が近いことが、子供にとっての使いやすさに繋がります。
- 現在の収納スペースに余裕はあるか?: ランドセルだけでなく、教科書、絵の具セット、習字道具など、学用品は年々増えていきます。これらのアイテムをまとめて収納できるスペースが確保できるかを確認しましょう。
- お子様の性格は?: 「自分の基地」のような専用スペースがあることで、やる気になるタイプのお子様には、ランドセルラックが良いきっかけになるかもしれません。
これらの点を総合的に考え、専用のラックを導入することが「片付けの習慣化」という目標達成への近道になると判断した場合に、購入を検討するのが賢明です。
なぜ?ありがちなランドセルラックの失敗パターン
せっかく購入したランドセルラックが、いつの間にかただの物置きになっていたり、子供部屋の隅でホコリをかぶっていたり…。そんな悲しい事態は避けたいものです。ここでは、実際に多くのご家庭で見られるランドセルラックの典型的な失敗パターンを3つご紹介します。これらの失敗例を知ることが、成功への第一歩です。
失敗例1:「とりあえず置くだけ」で物置き化してしまう
最も多い失敗が、ランドセルをラックの一番上に「ただ置くだけ」で終わってしまうケースです。これでは、重いランドセルを置くためだけの台になってしまい、ラックが持つ本来の収納機能が全く活かされません。棚や引き出しには関係のないおもちゃが詰め込まれ、教科書やプリントは結局ダイニングテーブルの上に出しっぱなし…。これでは、片付けの習慣が身につくどころか、かえって乱雑な印象を与えてしまいます。ラックを導入する目的が、親子間で共有できていない場合に起こりやすい失敗です。
失敗例2:子供の成長に合わなくなり使われなくなる
小学校低学年の時期は喜んで使っていても、高学年になるにつれて使われなくなるパターンです。この原因の多くは、購入時に子供の好みだけを優先しすぎたデザイン選びにあります。可愛らしいキャラクターが描かれたものや、あまりに子供っぽい配色のラックは、成長とともに子供自身が「恥ずかしい」と感じるようになり、次第に使わなくなってしまいます。6年間という長い期間使うものであることを念頭に置き、成長しても飽きずに使えるデザインかどうか、という視点が欠けていると、このような失敗に陥りがちです。
失敗例3:設置場所が悪く、生活動線の邪魔になる
子供の使いやすさを無視した場所に設置してしまうのも、失敗の大きな原因です。例えば、子供が帰宅してリビングを通って手洗い・うがいをする動線なのに、ランドセルラックだけが玄関から離れた子供部屋にあると、わざわざ置きに行くのが面倒になり、結局リビングの床にランドセルが放置される…ということになりかねません。子供の毎日の生活動線をよく観察し、その流れの中にスムーズに組み込める場所に設置することが、ラックを有効活用するための絶対条件です。
失敗を成功に変える!ランドセルラックの上手な活用方法
失敗パターンを反面教師にすれば、ランドセルラックを「本当に使える」有益な家具へと変えることができます。ここでは、子供が自ら進んで片付けをしたくなるような、上手な活用方法のコツを3つの視点からご紹介します。
「ただいま」から「宿題」までの動線を意識した仕組みづくり
成功の鍵は、ラックを単体で考えるのではなく、「帰宅後の一連の行動」という流れ(動線)の中に組み込むことです。例えば、「玄関で靴を脱ぐ→リビングのラックにランドセルを置く→中から連絡帳とプリントを出す→所定のトレーに入れる→手を洗う→おやつを食べる→宿題をする」というように、一連の動作がスムーズに行える場所にラックを配置し、収納の仕組みを作ります。この流れが習慣化すれば、子供は無意識に片付けを行えるようになります。
子供が自分で管理できる「見える化」収納のコツ
子供が自分で持ち物を管理するためには、「どこに何があるか」が一目でわかる「見える化」が非常に効果的です。引き出しやボックスには、「きょうかしょ」「のーと」「ぷりんと」といったように、ひらがなで書いたラベルを貼りましょう。まだ字が読めないお子様の場合は、イラストや写真を使っても良いでしょう。教科ごとに色分けしたファイルボックスを活用するのもおすすめです。中身が見える半透明の引き出しを選ぶなど、子供の「探す」手間を省いてあげることが、自分でできる自信に繋がります。
親子で決める「定位置管理」のルール
ラックを導入したら、まずはお子様と一緒に「どこに何を置くか」という定位置のルールを決めましょう。この時、親が一方的に決めるのではなく、「教科書は取りやすいこの段がいいかな?」「明日のハンカチは、この引き出しに入れておこうか」というように、子供の意見を尊重しながら決めることが大切です。自分で決めたルールであれば、子供も責任感を持ち、積極的に守ろうとします。「使い終わったら、必ず元の場所に戻す」という基本的な約束事を最初に共有することが、ラックをきれいに保つ秘訣です。
後悔しない!失敗しないランドセルラックの選び方
最後に、購入段階で失敗しないための、具体的なランドセルラックの選び方を3つの重要なポイントに絞って解説します。デザインや価格だけでなく、機能性や安全性、将来性まで見据えて選ぶことが、長く愛用できる一台を見つけるための鍵となります。
ポイント1:卒業後も見据えた「長く使える」デザインか
6年間は長いようで短い期間です。失敗例でも挙げたように、子供っぽいデザインは高学年になると使われなくなるリスクがあります。選ぶべきは、木目調のナチュラルなものや、白やグレーを基調としたシンプルなデザインのラックです。このような普遍的なデザインであれば、小学校卒業後も、中高生の学習用品を収納する棚として、あるいは大人の書斎やリビングの収納家具として、ライフステージの変化に合わせて長く使い続けることができます。棚板の高さが変えられる可変性の高いタイプなら、収納物に合わせて使い方を最適化できるため、さらに活用の幅が広がります。
ポイント2:収納力とサイズのバランスは適切か
ランドセルラックを選ぶ際は、「ランドセル+α」の収納力を考慮することが不可欠です。教科書やノートはもちろん、A4サイズのフラットファイル、絵の具セット、習字道具、鍵盤ハーモニカなど、学年が上がるにつれて学用品は驚くほど増えていきます。これらのアイテムがきちんと収まるかどうか、棚の奥行きや引き出しのサイズを確認しましょう。また、十分な収納力を確保しつつも、設置したい部屋のスペースに圧迫感なく収まるサイズであることも重要です。購入前には必ず設置場所の寸法を測り、ラックを置いた際の生活動線もイメージしておきましょう。
ポイント3:子供の安全性を考慮した素材と設計か
子供が毎日使う家具だからこそ、安全性には最大限の配慮が必要です。まず確認したいのは、製品の角が丸く処理されている「ラウンド加工」が施されているかどうかです。万が一、子供がぶつかってしまっても怪我のリスクを低減できます。また、シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの発散量が少ないことを示す「F☆☆☆☆(フォースター)」規格の素材を使用しているかどうかも、重要なチェックポイントです。さらに、子供が引き出しに寄りかかったりしても倒れにくい、安定感のある設計であることも確認しておくと、より安心して使用できます。
まとめ
ランドセルラック選びにおける「失敗」とは、多くの場合、ご家庭のライフスタイルや子供の成長という視点が抜けていることに起因します。ラックは単なる「物を置く箱」ではありません。子供の自立心を育み、家族の暮らしをスムーズにするための「仕組み(システム)」と捉えることが大切です。今回ご紹介した失敗例と、そこから導き出される活用法・選び方を参考に、ぜひ親子で話し合いながら、ご家庭にとって最適で、長く愛せる一台を見つけてください。その一台が、お子様の健やかな成長を支える、頼もしい相棒となってくれるはずです。