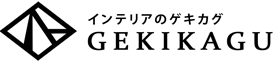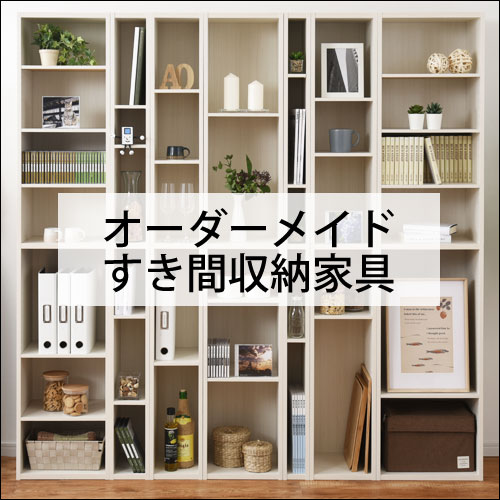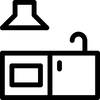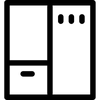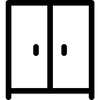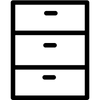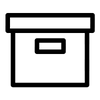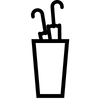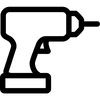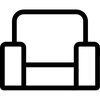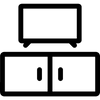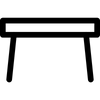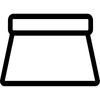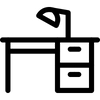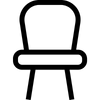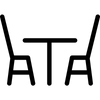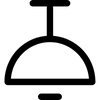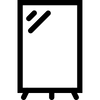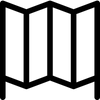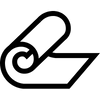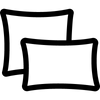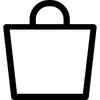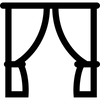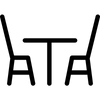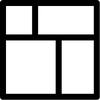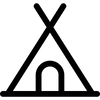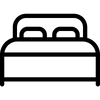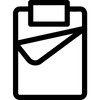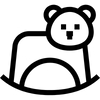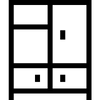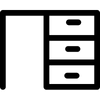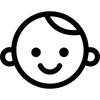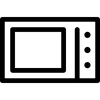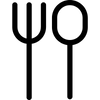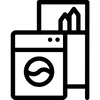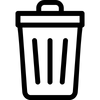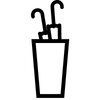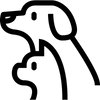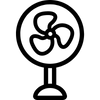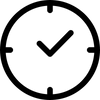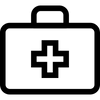押入れやクローゼットの中で、一番スペースを取り、出し入れが重くて大変な「布団」。重ねて置くと下の布団が取り出せず、床に直置きすると湿気やカビが心配…。そんな布団収納の尽きない悩みを、DIY(自作)で解決してみませんか?
市販のラックでは「サイズが微妙に合わない」「キャスターがなくて掃除が大変」といった不満も、手作りならすべて解消できます。押入れのスペースに1cm単位で合わせる「シンデレラフィット」はもちろん、通気性や強度、機能性まで、あなたの理想を形にできるのがDIYの最大の魅力です。
この記事では、重い布団を乗せても安心な「頑丈な布団収納ラック」を手作りするための、材料選びから組み立て手順、そして最も重要な強度アップの秘訣まで、徹底的にガイドします。
STEP1:設計と材料の準備【すべては正確な採寸から】
DIYの成功は、準備段階で決まります。特に布団収納ラックは、「収納場所」と「収納物」の両方を正確に把握することが重要です。
設計のポイント:湿気と重さに打ち勝つ構造を
- 正確な採寸: まず、ラックを設置したい押入れやクローゼットの「幅・奥行き・高さ」を正確に測ります。この時、押入れの「中段」や「ふすまの枠」なども考慮し、スムーズに出し入れできるサイズを割り出します。
- 機能性の決定: 掃除のしやすさを考え、重い布団を乗せたまま動かせる**「キャスター付き」**の台車(ワゴン)型ラックの設計図を描くのが最もおすすめです。
- 通気性の確保: 布団は湿気を嫌います。底板はベニヤ板などで塞がず、**「すのこ状」**にして空気の通り道を確保する設計にします。
ホームセンターで揃える!材料選び
● 木材(フレーム・棚板用):
○ SPF材(1×4材、2×4材): 安価で加工しやすく、十分な強度が出せるDIYの定番木材です。土台のフレームや重さのかかる部分には「2×4材」、すのこ状の棚板部分には「1×4材」を使うなど、使い分けるのがおすすめです。
○ 桐(きり)すのこ: 既にすのこ状になっている市販の「桐すのこ」を底板として活用するのも非常に賢い方法です。桐は軽量で調湿効果にも優れ、布団収納に最適です。
● キャスター(4〜5個):
○ 最重要パーツです。 布団は見た目以上に重く(敷布団1枚で5kg以上)、ラック本体の重量も加わります。必ず**「耐荷重」を確認し、4つのキャスターの合計耐荷重が、収納したい布団の総重量+ラック本体重量の1.5倍以上**になる余裕を持った製品を選びましょう。
● ビス(木ネジ):
○ 木材の厚みに合わせた長さの「コーススレッド」が、保持力が高くおすすめです。
● 木工用ボンド: 強度アップのための必須アイテムです。
STEP2:必要な工具の準備
安全で正確な作業のために、基本的な工具を揃えましょう。
● 電動ドライバー(インパクトドライバー推奨): 布団ラックは強度を出すために多くのビスを打ちます。パワーのあるインパクトドライバーがあると、作業が格段に楽で確実になります。
● 下穴用ドリルビット: ビスを打つ前に使う、木材の割れを防ぐ重要アイテムです。
● メジャー、さしがね: 正確な採寸と直角を出すための必需品。
● サンドペーパー(紙やすり): カットした木材のささくれ(バリ)を取り除き、布団を引っ掛けないよう滑らかにするために使います。
● (あれば)クランプ: 木材を固定する際に使うと、一人でも作業が格段に安定します。
STEP3:組み立て手順【キャスター付きワゴン型ラック編】
ここでは、押入れ下段に最適な、キャスター付きの台車型ラックの作り方を解説します。
-
土台フレーム(枠)の組み立て
設計したサイズにカットした木材(例:2×4材)で、ラックの土台となる四角い枠(「ロ」の字型)を組みます。さしがねを使い、全ての角が直角になるよう注意深く確認しながら、各コーナーをビスで固定します。 -
底板(すのこ)の取り付け
組んだ土台フレームの上に、底板となる木材(例:1×4材)を渡していきます。ここで**重要なのが「湿気対策」**です。板同士をぴったりくっつけず、1〜2cmほどの隙間を空けながらビスで固定し、「すのこ状」に仕上げます。 -
【任意】落下防止の柵(手すり)の取り付け
押入れから引き出す際に布団が横からずり落ちるのを防ぐため、ラックの左右や奥に、落下防止用の簡単な柵(例:1×4材や丸棒)を取り付けると、より使いやすくなります。 -
キャスターの取り付け
ラックを裏返し、土台フレームの四隅にキャスターをビスでしっかりと固定します。この時、キャスターの車輪がスムーズに回転できるよう、向きを揃えて取り付けるのがコツです。
STEP4:【最重要】布団の重さに負けない!強度を上げる鉄壁のテクニック
DIYの布団ラックで最も怖いのは、重さによる破損です。以下のテクニックで、プロが作ったような頑丈なラックに仕上げましょう。
秘訣1:最強の耐荷重「日」の字構造+キャスター5点留め
布団の重さは中央に集中し、たわみの原因となります。これを防ぐため、土台フレームを「ロ」の字型ではなく、中央にもう一本、梁を渡した**「日」の字型に組みましょう。この中央の梁が、すのこ状の底板を真下から支え、強度を劇的に向上させます。
さらに、四隅のキャスターに加え、この中央の梁の下にもう一つキャスターを取り付ける「5点留め」**にすることで、荷重が分散され、ラック全体の安定感と耐久性が格段にアップします。
秘訣2:「木工用ボンド」と「ビス」の併用
木材同士を接合する際、ビスで留める前に、必ず接合面に木工用ボンドを塗布してください。ボンドが乾燥することで木材が一体化し、ビスだけの固定とは比べ物にならないほどの「ねじれ」や「歪み」に対する強度を生み出します。
秘訣3:「下穴」は強度を保つための必須工程
ビスを直接打ち込むと、木材が割れてしまい、そこから強度が著しく低下します。ビスを打つ場所には必ず、ビスの太さより一回り細い「下穴」をドリルで開ける習慣をつけましょう。これにより木割れを防ぎ、ビスの保持力を最大化できます。
秘訣4:「L字金具」で見えない角を補強する
土台フレームの内側の四隅など、特に大きな力がかかるコーナー部分には、「L字金具」を追加で取り付けて補強しましょう。大きな負荷がかかった際のぐらつきを防ぎ、ラック全体の剛性を高める最後の砦となります。
DIYで叶える「出し入れ簡単」な布団収納ライフ
今回は、布団収納ラックのDIYについて、湿気と重さ対策、そして強度アップの秘訣を中心にご紹介しました。
市販品では叶わなかった「あと数センチ」のこだわりや、「ここにもう一つ機能が欲しい」という願いを、自分の手で形にできるのがDIYの醍醐味です。押入れの奥で眠っていたスペースが、キャスター付きのラックで機能的な収納へと生まれ変わる瞬間は、何物にも代えがたい達成感を与えてくれるでしょう。
ぜひこの記事を参考に、安全で頑リなラック作りに挑戦し、毎日の布団の出し入れを快適にしてください。