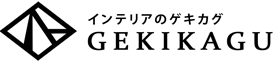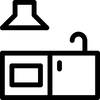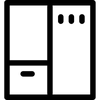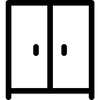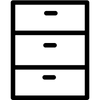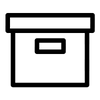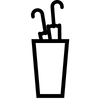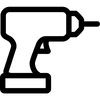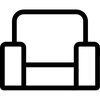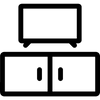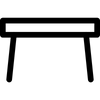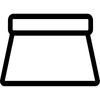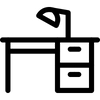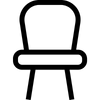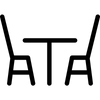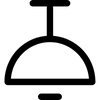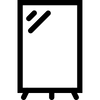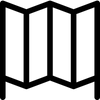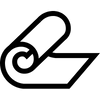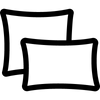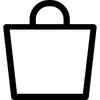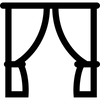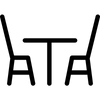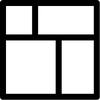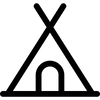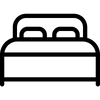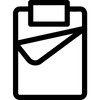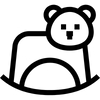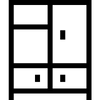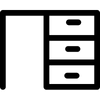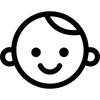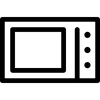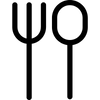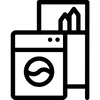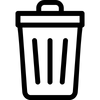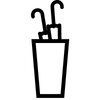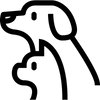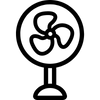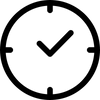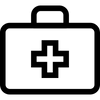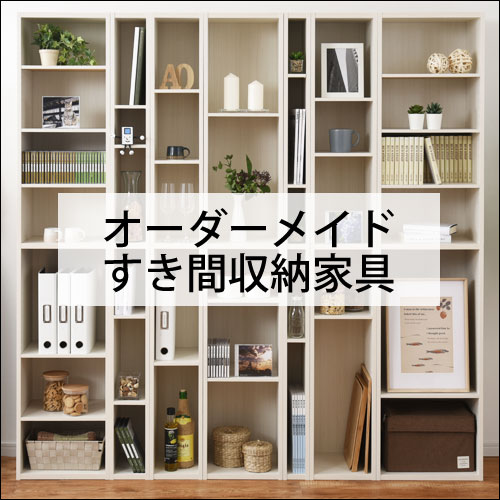お部屋の隙間にぴったりの棚、理想のテイストに合ったシェルフ、大量の本をしっかり支えてくれる丈夫な本棚…。市販品を探しても、なかなか「これだ!」というものに出会えないことはありませんか?そんな願いを叶えてくれるのが、自分の手で作り上げる「ラックの自作(DIY)」です。
そして、その最強のパートナーとなるのが、あらゆる資材や道具が揃う「ホームセンター」。一見ハードルが高そうに見えるラック作りも、ポイントを押さえてホームセンターを賢く活用すれば、DIY初心者でも驚くほど本格的なものが作れるのです。
この記事では、設計から材料選び、組み立ての基本手順、そして長く安心して使うための最も重要な「強度を上げる方法」まで、ラック自作の全工程を徹底ガイドします。
なぜ自作?ホームセンターでラックを作る3つの魅力
お気に入りの本をすっきり整理。使いやすさが光る本棚・ラック特集
 > 特集ページはこちらから <
> 特集ページはこちらから <

既製品を買うのとは違う、自作ならではの特別な価値とは何でしょうか。
-
置きたい場所に「シンデレラフィット」
自作ラック最大の魅力は、置きたいスペースに合わせて1mm単位でサイズを設計できることです。家具と壁の間のわずかな隙間、部屋の隅のデッドスペースなど、既製品では活かせなかった場所にぴったりの「シンデレラフィット」な収納が実現します。 -
デザインも素材も想いのまま
温かみのあるパイン材、安価で加工しやすいSPF材、無骨でかっこいいアイアンパーツの組み合わせなど、材料選びから自由自在。塗装の色を変えたり、ワックスでヴィンテージ風に仕上げたりと、あなたのお部屋のテイストに完璧にマッチした、世界に一つだけのオリジナルデザインを追求できます。 -
既製品より「高コスパ」も実現可能
材料の選び方や設計の工夫次第では、同等サイズの既製品を購入するよりもコストを抑えることが可能です。特に、ホームセンターのカットサービスなどをうまく利用すれば、高価な工具を揃える必要もなく、経済的にDIYを楽しめます。
STEP1:設計と材料の準備【ホームセンターへ行く前に】
成功への道は、ホームセンターへ行く前の準備から始まっています。いきなりお店に行っても、膨大な資材を前に迷ってしまうだけです。
まずは簡単な「設計図」を描こう
正確なDIYの第一歩は、完成形をイメージした設計図を描くことです。立派なものである必要はありません。手書きの簡単なイラストで十分です。
- 採寸: ラックを置きたい場所の「幅・高さ・奥行き」を正確に測ります。
- 外寸決定: 採寸したスペースに収まるラックの外寸を決めます。
- 棚板の枚数と位置決め: 何段の棚にするか、棚と棚の間隔をどのくらいにするかを決めます。
- 材料リスト作成: 設計図をもとに、必要な木材の「長さ」と「本数」をすべて書き出します。これが「木取り図(カットリスト)」になります。
ラック自作におすすめの材料(木材)
ホームセンターの木材コーナーには様々な種類がありますが、初心者が扱いやすいのは以下の木材です。
● SPF材(エスピーエフざい): 安価で柔らかく、加工しやすいDIYの定番木材。「2×4(ツーバイフォー)材」や「1×4(ワンバイフォー)材」といった規格サイズで販売されており、入手しやすいのが魅力です。
● パイン集成材: 明るい色味で木目が美しいのが特徴。比較的柔らかく、テーブルの天板などにも使われます。SPF材よりは少し高価ですが、ナチュラルな雰囲気のラックに仕上がります。
● 合板(ごうはん): 薄い板を何層にも重ねて圧着した木材。OSB合板など、独特の模様を活かしたインダストリアルなデザインも人気です。
賢く使おう!ホームセンターの「木材カットサービス」
ほとんどのホームセンターには、購入した木材を指定した寸法にカットしてくれる有料サービスがあります。DIY初心者こそ、このサービスを積極的に活用しましょう。正確な直線・直角カットは、美しい仕上がりと強度に直結します。自分でノコギリを使って切る手間と失敗のリスクを考えれば、非常に価値のあるサービスです。
STEP2:これだけは揃えたい!必須の工具と道具
次に、ラック作りに必要な工具を準備します。最初から全てを揃える必要はありませんが、以下のものは作業効率と仕上がりを大きく左右します。
【必須】基本の工具
● 電動ドライバー(ドリルドライバー): ビス(ネジ)を打ち込む作業が驚くほど楽になります。手でドライバーを回すのに比べ、時間も労力も大幅に削減。DIYの必須アイテムです。
● メジャー: 正確な採寸と印付けの基本。
● さしがね: 材料に対して直角の線を引いたり、直角を確認したりするのに使います。
● 水平器: 棚板が傾いていないか、まっすぐに取り付けられているかを確認するための必需品。最近ではスマートフォンのアプリでも代用できます。
【あると便利】作業がはかどる道具
● クランプ: 木材同士を接着したり、ビスで固定したりする際に、材料をガッチリと押さえておくための道具。一人での作業でも、安全かつ正確に行えます。
● サンドペーパー(紙やすり): 木材のカット面のささくれを取り除き、手触りを滑らかにします。塗装前の下地処理にも使います。
● 下穴(したあな)用ドリルビット: 電動ドライバーの先端に取り付けて、ビスを打つ前に小さなガイド穴を開けるための刃。木材の割れを防ぐ重要な役割があります。
STEP3:いよいよ実践!基本の組み立て手順
準備が整ったら、いよいよ組み立てです。ここでは、最も基本的な四角い木製ラックの作り方を例にご紹介します。
-
墨付け(すみつけ)とヤスリがけ
設計図通りに、全ての支柱となる木材に、棚板を取り付ける位置を正確に鉛筆で印付け(墨付け)します。さしがねを使い、全ての支柱が同じ高さになるよう、丁寧に線を引きましょう。この時、カットした木材の角やささくれをサンドペーパーで滑らかにしておくと、安全で仕上がりも美しくなります。 -
枠組みの組み立て
いきなり全体を組むのではなく、まずはラックの左右の側面となる「はしご」のような形のパーツから組み立てます。2本の支柱に、棚板をビスで固定していきます。さしがねを使って、支柱と棚板がしっかりと直角になっているかを確認しながら作業するのが、歪みをなくす重要なポイントです。 -
棚板の取り付けと全体の完成
組み上げた2つの側面の枠を立て、その間に残りの棚板を渡して固定していきます。墨付けした位置に棚板を乗せ、水平器で傾きがないかを確認しながら、ビスでしっかりと固定します。一枚ずつ丁寧に取り付けていけば、ラックの形が完成です。
STEP4:プロの仕上がり!ラックの強度を上げる方法
自作ラックを長く安心して使うために、最も重要なのが「強度」です。少しの手間で見違えるほど頑丈になります。
【基本のキ】木割れを防ぐ「下穴」を開ける
ビスを打ち込む前に、必ずビスの太さより一回り細いドリルビットで「下穴」を開けましょう。これは、ビスが木材の繊維を無理やり押し広げて割ってしまうのを防ぐための、基本中の基本テクニックです。特に、木材の端に近い部分にビスを打つ際は必須の工程です。
【ぐらつき防止の最強技】「背板」または「筋交い」を入れる
完成したラックを手で揺らしてみて、横揺れやぐらつきを感じる場合は補強が必要です。最も効果的なのが、ラックの背面に薄いベニヤ板などで「背板」を張ること。箱状になることで全体の剛性が一気に高まり、横揺れをほぼ完璧に防ぎます。
デザイン的に背面を開放したい場合は、バツ印に板を渡す「筋交い(すじかい)」を入れたり、各コーナーの内側にL字金具を取り付けたりするだけでも、強度は格段にアップします。
【耐荷重アップ】「L字金具」で棚板をしっかり支える
本や家電など、重いものを乗せる棚には、棚板の下に「L字金具」を取り付けて支えを追加しましょう。棚板が重みでたわむのを防ぎ、耐荷重を大幅に向上させることができます。最近では、デザイン性の高いアイアン製のL字金具も多く、見せる補強パーツとしておしゃれなアクセントにもなります。
世界に一つのラックと、DIYのある暮らしを
今回は、ホームセンターを活用した自作ラックの作り方を、準備から強度アップの秘訣まで一貫してご紹介しました。
正確な設計図とホームセンターのカットサービス、そして強度を高めるためのちょっとしたコツ。これさえ押さえれば、DIY初心者でも既製品に負けない、愛着のわくオリジナルラックを作ることができます。自分で作った家具が暮らしの中にある喜びは、何物にも代えがたいものです。ぜひこの記事をガイドブックに、あなただけのラック作りに挑戦してみてください。