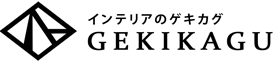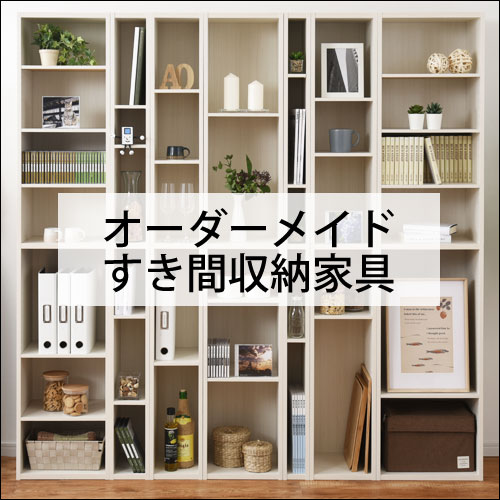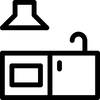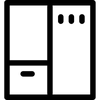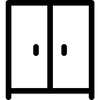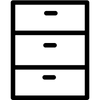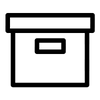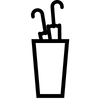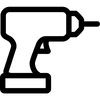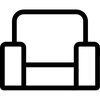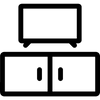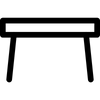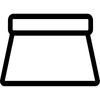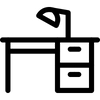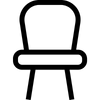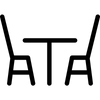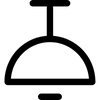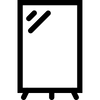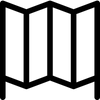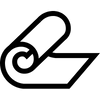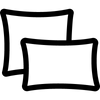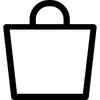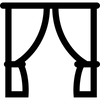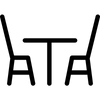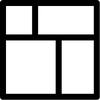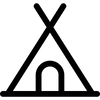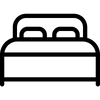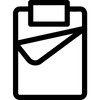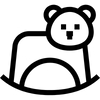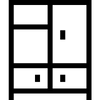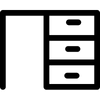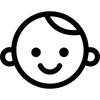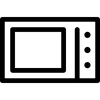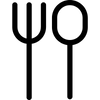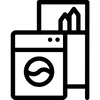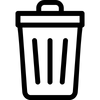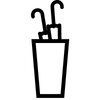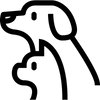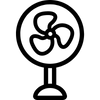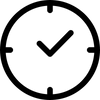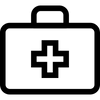お部屋の一角に、ごろんと寝転がれる畳の小上がり。そんな、カフェや旅館のようなリラックス空間が自宅にあったら素敵だと思いませんか?しかし、本格的なリフォームとなると費用も時間もかかり、賃貸ではほぼ不可能です。そこでおすすめしたいのが、収納家具の王様「カラーボックス」を土台にした小上がりのDIYです。アイデア次第で、収納力抜群のおしゃれな小上がりを、驚くほど低コストで実現できます。
この記事では、その不安を解消するため、安全で頑丈な小上がりを作るための設計の考え方から、材料選び、組み立て手順、そして最も重要な強度を上げるためのプロの秘訣まで、徹底的に解説します。
なぜ人気?カラーボックスで小上がりをDIYするメリット
DIYのアイデアは数あれど、なぜカラーボックスを使った小上がりがこれほど人気なのでしょうか。それには大きな3つの魅力があります。
-
圧倒的な収納力の確保
小上がり全体が、一つの巨大な収納庫になります。カラーボックスの各棚が、普段使わない季節家電や衣類、本、防災グッズなどをたっぷりと収納するスペースに早変わり。デッドスペースになりがちな部屋の角が、機能的な収納スペースへと生まれ変わります。 -
驚きの低コストパフォーマンス
木材をゼロから組んでいく本格的な造作に比べ、土台の大部分を安価なカラーボックスで代用するため、材料費を劇的に抑えることが可能です。ホームセンターやインテリアショップで手軽に入手できる材料だけで作れるのも、大きな魅力です。 -
賃貸でも可能な「置くだけ」設置
床や壁に直接ビスを打ったり接着したりせず、単に「置くだけ」の構造にすれば、賃貸住宅でも原状回復が可能です。引っ越しの際には解体して部材を再利用したり、移動させたりすることもできます。
STEP1:設計と材料の準備【強度を左右する最重要工程】
楽しいDIYですが、人が乗る小上がり作りでは、設計と材料選びの段階が最も重要です。ここで手を抜くと、安全性に直結します。
設計のポイント:強度確保は「骨組み」が9割
カラーボックスは、あくまで土台の一部。その上に人が乗るための頑丈なステージを木材で組む、というイメージを持ってください。
● カラーボックスの配置: 作りたい小上がりのスペースに、カラーボックスを隙間なく敷き詰めるように配置図を描きます。面積が広い場合は、中央部分の「たわみ」を防ぐため、真ん中にも支えとなるカラーボックスや木材の脚を入れる計画を立てます。
● 天板の構造: カラーボックスの上に直接薄い板を乗せるだけでは絶対に強度が足りません。カラーボックスの上に、2×4(ツーバイフォー)材などで格子状の骨組み(建築用語で「根太(ねだ)」と言います)を組み、その上に厚い板を乗せる二重構造を基本とします。
材料選びのコツ:人が乗ることを前提に選ぶ
● カラーボックス: 安価すぎると中がスカスカな場合があります。できるだけ重量があり、中のパーティクルボードがぎっしり詰まった、しっかりとした製品を選びましょう。棚板がネジで固定されているタイプがより頑丈でおすすめです。
● 天板: 人の体重を分散して支える重要なパーツです。厚さ12mm以上の構造用合板(コンパネ)やOSB合板を選びましょう。
● 骨組み(根太): 天板を面で支える骨組みには、丈夫で歪みの少ない2×4材や2×2材が適しています。
● 仕上げ材: 天板の上に敷くもの。半畳サイズの置き畳(琉球畳)や、タイルカーペット、厚手のクッションフロアなど、お好みのものを用意します。
STEP2:必要な工具の準備
安全で正確な作業のために、以下の工具はぜひ揃えておきましょう。
● 電動ドライバー(特にインパクトドライバー): 長いビスを何十本も打ち込むため、パワーのあるインパクトドライバーがあると作業効率が劇的に上がります。
● メジャー、さしがね: 正確な採寸と、直角を出すための必需品です。
● ノコギリ: 木材をご自身でカットする場合に必要です。ホームセンターの木材カットサービスを利用すれば、この手間を省けます。
● 木工用ボンド、ビス(ネジ): 強度確保の重要アイテムです。
STEP3:強度を最優先した組み立て手順
いよいよ組み立てです。一つひとつの工程で「強度」を意識しながら、丁寧に作業を進めましょう。
-
土台となるカラーボックスの連結・固定
設計図通りに、設置したい場所にカラーボックスを並べます。そして、隣り合うカラーボックス同士を、内側から連結用の金具や短いビスで何か所もしっかりと固定し、全体がズレたり動いたりしないよう、一つの大きな塊にします。この工程が、完成後のぐらつきを防ぐ第一歩です。 -
天板を支える骨組み(根太)の設置
連結したカラーボックスの上に、2×4材などで格子状の骨組みを組んでいきます。まず外周を「ロ」の字型に組み、次に内側を30cm〜45cm程度の間隔で格子状になるよう木材を渡していきます。木材同士が交差する部分は、長いビスで斜め打ちするなどして、強固に固定してください。 -
天板の固定と仕上げ
完成した骨組みの上に、カットした構造用合板を乗せます。そして、骨組みの木材に向かって、30cm間隔を目安にまんべんなくビスを打ち込み、天板を完全に固定します。天板のフチだけでなく、中央部分にもしっかりとビスを打つことが「たわみ」を防ぐポイントです。
最後に、天板の上にお好みの置き畳やタイルカーペットを敷き詰めれば、小上がりの完成です!
【最重要】カラーボックス小上がりの強度をさらに上げるプロの技
安心して長く使うために、設計・組み立ての段階でぜひ取り入れてほしい、強度アップの秘訣をご紹介します。
秘訣1:中央部の「束(つか)」でたわみを徹底的に防ぐ
小上がりの面積が畳2枚分以上になるなど広い場合、最も体重がかかり、たわみやすいのが中央部分です。これを防ぐ最も効果的な方法が、床から天板の骨組み(根太)を直接支える「束(つか)」と呼ばれる短い柱を追加することです。カラーボックスを置いていない中央の空間に、床から骨組みまでの高さにぴったりカットした2×4材などを垂直に立てるだけで、強度は劇的に向上します。
秘訣2:見えない部分で「カラーボックス自体」を補強する
カラーボックスの背板は薄くて強度がないため、最初から取り付けないか、外してしまいましょう。そして、箱の歪みを防ぐため、内側の角をL字金具で補強したり、棚板の奥に縦方向に補強の板を一本追加したりするのも非常に効果的です。
秘訣3:最強の組み合わせ「ビス」と「木工用ボンド」の併用
木材と木材を接合する際、ビスで留める前に、接合面に木工用ボンドを塗っておきましょう。ボンドが乾燥すると木材が一体化し、ビスだけの固定に比べてねじれや歪みに対する強度が格段にアップします。これはプロの大工も使う、簡単ながら非常に効果的なテクニックです。
DIYで創る、私だけの特等席。安全な小上がりで暮らしが変わる
今回は、カラーボックスを土台にした小上がりのDIYについて、多くの方が不安に思う「強度」に焦点を当てて詳しく解説しました。
安価なカラーボックスはあくまで土台の一部と割り切り、その上に頑丈な骨組みと厚い天板を組み合わせることが、安全な小上がりを作る絶対条件です。ご紹介した「根太」や「束」といったプロの技を取り入れれば、DIY初心者でも安心してくつろげる、頑丈な小上がりは必ず作れます。
ぜひこの記事を参考に、あなただけの特別なリラックススペース作りに挑戦してみてください。