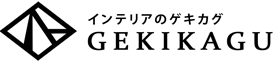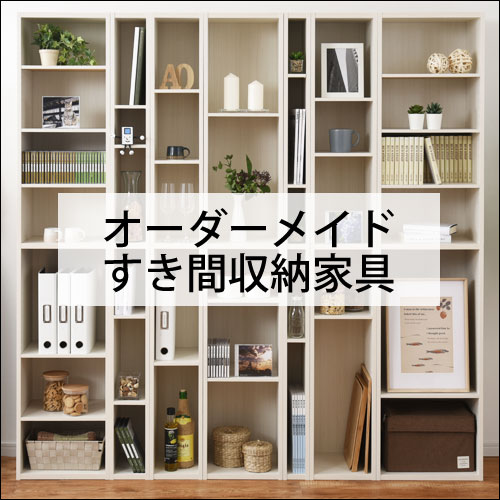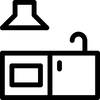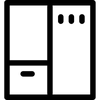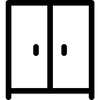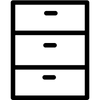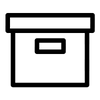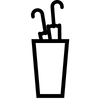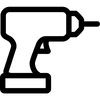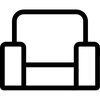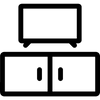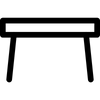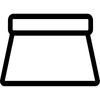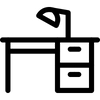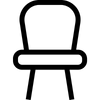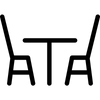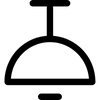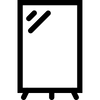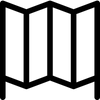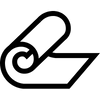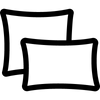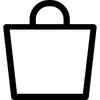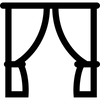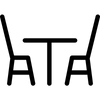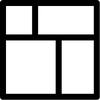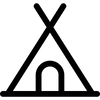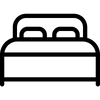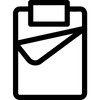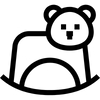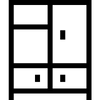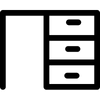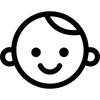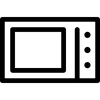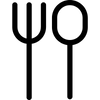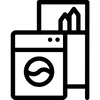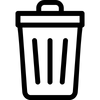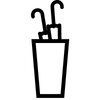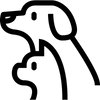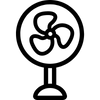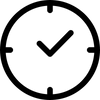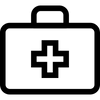開けるたびに中身が混ざり合い、探している物が見つからない「カオスな引き出し」。この記事では、そんな悩みを根本から解決するための具体的な方法を、収納のプロの視点で徹底的に解説します。まず、引き出しが片付かない原因を分析し、次にどんな引き出しにも応用できる収納の「黄金ルール」を4つのステップでご紹介。さらに、キッチンやデスク、衣類といった場所別の賢い収納術から、100円ショップなどで手に入る便利な仕切りグッズまで、すぐに実践できるアイデアを満載しました。この記事を読めば、あなたの引き出しは機能的で美しい収納スペースへと生まれ変わります。
なぜ?あなたの引き出しが「ブラックボックス」になる3つの理由
「引き出しの中は、そもそも収納のためにあるはずなのに、なぜかいつもごちゃごちゃ…」。そう感じている方は少なくないでしょう。閉めてしまえば見えない安心感から、いつしか中身が謎に包まれた「ブラックボックス」と化してしまう。この問題には、実は多くの人に共通するいくつかの原因があります。まずはその原因を理解することが、片付け成功への第一歩です。
原因1:仕切りがなく、モノが混ざり合っている
引き出しの中が片付かない最大の原因は、内部に「仕切り」がないことです。広々とした一つの空間に、大きさも形も用途も違う様々なモノをそのまま入れると、引き出しを開閉するたびに中身が動き、自然と混ざり合ってしまいます。カトラリーも、文房具も、靴下も、仕切りがなければすべてが一つの大きな塊になってしまうのです。これでは、目的の物を探すのに時間がかかるだけでなく、片付ける意欲そのものも失われてしまいます。
原因2:「とりあえず」の放り込みが習慣化している
忙しい毎日の中で、「後で片付けよう」と、とりあえず引き出しに物を放り込む習慣はありませんか。ペン1本、輪ゴム1つ、DM1枚。その一つ一つは些細なことですが、この「とりあえず収納」が積み重なることで、引き出しの中はあっという間に飽和状態になります。本来あるべき場所に戻すという一手間を惜しむことが、結果的に引き出し全体の機能を麻痺させてしまうのです。
原因3:中に入っているモノの全体量を把握していない
あなたの家の引き出しに、何がどれくらい入っているか、正確に答えられるでしょうか。多くの場合、引き出しの奥の方には何年も使っていない物や、同じような物がいくつも眠っています。中身の全体像を把握できていないため、不要な物を溜め込み続け、本当に必要な物のためのスペースがなくなってしまうのです。これが、引き出しが常にパンパンで使いにくい状態を生み出す根本的な原因となっています。
カオスな引き出しを卒業!収納を始める前の「4つの黄金ルール」
引き出しが片付かない原因がわかったら、いよいよ実践です。しかし、やみくもに整理を始めても、またすぐに元通りになってしまいます。ここでは、どんな引き出しにも応用できる、リバウンドしないための「4日つの黄金ルール」をステップバイステップでご紹介します。
STEP1:まずは全部出す!「全出し」で現状を把握する
片付けの第一歩は、引き出しの中身をすべて出すこと、通称「全出し」です。少し面倒に感じるかもしれませんが、これは絶対に欠かせないプロセスです。中身をすべて広げることで、「こんな物があったのか」「同じ物がこんなに…」と、自分がどれだけの物を所有していたかを視覚的に認識できます。この現状把握が、次のステップである「分ける」作業の精度を高めるのです。
STEP2:「使う・使わない・迷う」に分ける勇気
全部出したら、次は一つ一つの物を「今、使っているか」という基準で、「使う」「使わない」「迷う」の3つに分類します。ポイントは「いつか使うかも」ではなく、「今」を基準に判断する勇気を持つことです。「使わない」と判断した物は潔く手放し、「迷う」物は一旦別の箱に入れて期限を決め、その日までに使わなければ手放す、というルールを設けるのも良いでしょう。
STEP3:使用頻度で決める「一軍・二軍」の定位置
「使う」と判断した物は、さらにその使用頻度によってグループ分けします。毎日使うハサミやペン、箸などは「一軍」。週に一度程度使うホッチキスや爪切りなどは「二軍」。このように使用頻度で分けることで、引き出しの中のどこに何を配置すべきか、という「定位置」が見えてきます。当然、一軍の物は最も取り出しやすい手前側に、二軍の物はその奥に配置するのが基本です。
STEP4:モノの住所を決める「ゾーニング(仕切り)」
最後に、分類したモノたちに「住所」を与える作業、それが「ゾーニング」です。市販の仕切りやトレー、空き箱などを活用して、引き出しの内部を細かく区切っていきます。「この区画はペン」「この区画はクリップ」というように、一つのグループに一つの住所を与えます。これにより、モノたちが混ざり合うのを防ぎ、使った後も自然と元の場所に戻せるようになります。
【場所別】引き出しの中の賢い収納術
黄金ルールをマスターしたら、次は場所ごとの特性に合わせた応用テクニックです。ここでは特に散らかりやすい3つの場所を例に、具体的な収納術をご紹介します。
キッチン編:カトラリーと調理器具を機能的に整理するコツ
キッチンの引き出しは、様々な形や大きさの物が集まる場所です。カトラリーは、専用のトレーを使って種類ごとに分けましょう。お弁当用のピックやおかずカップのような細々した物は、小さなケースにまとめて入れると「迷子」になりません。菜箸やおたまなどの長い調理器具は、引き出しのサイズに合ったケースで仕切ることで、転がりや絡まりを防ぎ、調理中の取り出しが格段にスムーズになります。
デスク周り編:文房具と書類をすっきり使いやすくする技術
デスクの引き出しは、浅いタイプが多いのが特徴です。ここでも仕切りトレーが大活躍します。ペン、クリップ、付箋など、種類ごとに細かくゾーニングしましょう。特におすすめなのが、使用頻度に応じた配置です。毎日使う一軍のペンやハサミは一番手前に。たまにしか使わない二軍のホッチキスやのりは二段目に、というように配置すれば、作業効率が大きく向上します。クリアファイルやファイルボックスを使えば、書類も立てて収納でき、必要な書類をすぐに見つけ出せます。
衣類編:「立てる収納」で一目瞭然のクローゼットへ
Tシャツや下着、靴下などを収納する引き出しは、「立てる収納」が鉄則です。衣類を畳んだ後、上に重ねるのではなく、引き出しの深さに合わせて立てて並べることで、引き出しを開けた瞬間にすべての衣類が見渡せます。これにより、下の服を取り出すために上を崩す必要がなくなり、いつでも綺麗な状態をキープできます。靴下や下着などの小物は、仕切りのついたケースを使うと、中でごちゃごちゃになるのを防げます。
収納上手のマストアイテム!引き出し整理に役立つ便利グッズ
最後に、カオスな引き出しを機能的な収納スペースに変えるための、心強い味方となる便利グッズをご紹介します。高価なものである必要はありません。身近なお店で手に入るアイテムを賢く活用しましょう。
自由自在に形を変えられる「仕切り板」
プラスチック製の板を十字に組んだり、好きな長さにカットしたりして使えるのが「仕切り板」です。引き出しのサイズや収納したい物に合わせて、オーダーメイドのように空間を区切ることができるのが最大の魅力。特に、靴下やハンカチといった小物の整理に非常に役立ちます。
サイズ豊富な「システムトレー」
様々なサイズのトレーをパズルのように組み合わせて使うのが「システムトレー」です。文房具やカトラリーなど、規格がある程度決まっている物の収納に最適です。同じシリーズで揃えれば、引き出しの中に無駄な隙間なく、ぴったりと美しい収納空間を作り出すことができます。
無印良品や100円ショップの隠れた名品
無印良品の「ポリプロピレン整理ボックス」や、100円ショップで手に入る様々なサイズのプラスチックケースは、引き出し収納の強い味方です。シンプルなデザインで汎用性が高く、家中のあらゆる引き出しに応用できます。まずはこれらのアイテムから試してみて、自分の家に合った収納スタイルを見つけていくのも良いでしょう。
まとめ
引き出しの中の収納を見直すことは、単に物を整理する以上の意味を持ちます。それは、自分の持ち物を管理し、探すという無駄な時間をなくし、日々の暮らしにゆとりを生み出すための、非常に効果的な自己投資です。閉めれば見えない小さな空間だからこそ、そこを美しく機能的に整えることができれば、生活全体の質が向上し、心にも余裕が生まれます。今回ご紹介した黄金ルールと具体的なテクニックを参考に、まずは一番気になる引き出し一つから、カオスからの卒業を目指してみませんか。